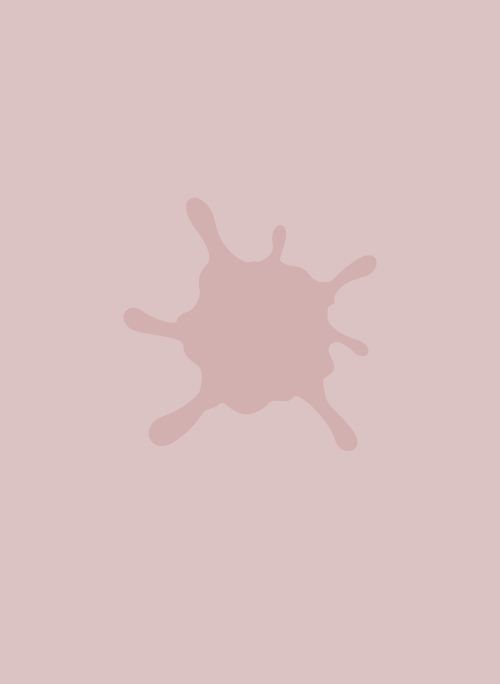「じゃ、そういうことだから」
わたしは彼の手が離れたのを見逃さず、その場を立ち去る。
彼のわたしへの返答は、暗に彼女と付き合うと告げていた。
食事の時もわたしは意図的に彼と目を合わせようとしなかった。
彼のお姉さんになりたかった。
兄弟になって、彼女ができたと聞かされて、からかえるような関係を望んでいたはずなのに、そんな関係を、台無しにしてしまったのもわたしだったのだ。
わたしは部屋に戻ると、行き場のない気持ちを抱えて泣いていた。
わたしと樹の微妙な関係とはお構いなく、半田君の誕生日の計画は着々と進行していた。
半田君へのプレゼントはケーキで決定した。その日集まるメンバーの希望を聞いたうえで、チョコレートケーキになり、予約も済ませていた。
樹と佐々木さんは付き合っていることを隠しているのか、樹が返事を保留しているのかは分からないが、二人が付き合っているという噂は流れていても、事実としては伝わっていなかった。
わたしも幾人かに真相はどうなのかと聞かれたが、分からないと答え続けていた。それは嘘ではない。
樹と登下校を一緒にしていても、佐々木さんの話は一切出てこなかった。
彼女の気配を感じることさえもなかった。
わたしは樹と仲直りができないまま、半田君の家に行く日を迎えた。
わたしは彼の手が離れたのを見逃さず、その場を立ち去る。
彼のわたしへの返答は、暗に彼女と付き合うと告げていた。
食事の時もわたしは意図的に彼と目を合わせようとしなかった。
彼のお姉さんになりたかった。
兄弟になって、彼女ができたと聞かされて、からかえるような関係を望んでいたはずなのに、そんな関係を、台無しにしてしまったのもわたしだったのだ。
わたしは部屋に戻ると、行き場のない気持ちを抱えて泣いていた。
わたしと樹の微妙な関係とはお構いなく、半田君の誕生日の計画は着々と進行していた。
半田君へのプレゼントはケーキで決定した。その日集まるメンバーの希望を聞いたうえで、チョコレートケーキになり、予約も済ませていた。
樹と佐々木さんは付き合っていることを隠しているのか、樹が返事を保留しているのかは分からないが、二人が付き合っているという噂は流れていても、事実としては伝わっていなかった。
わたしも幾人かに真相はどうなのかと聞かれたが、分からないと答え続けていた。それは嘘ではない。
樹と登下校を一緒にしていても、佐々木さんの話は一切出てこなかった。
彼女の気配を感じることさえもなかった。
わたしは樹と仲直りができないまま、半田君の家に行く日を迎えた。