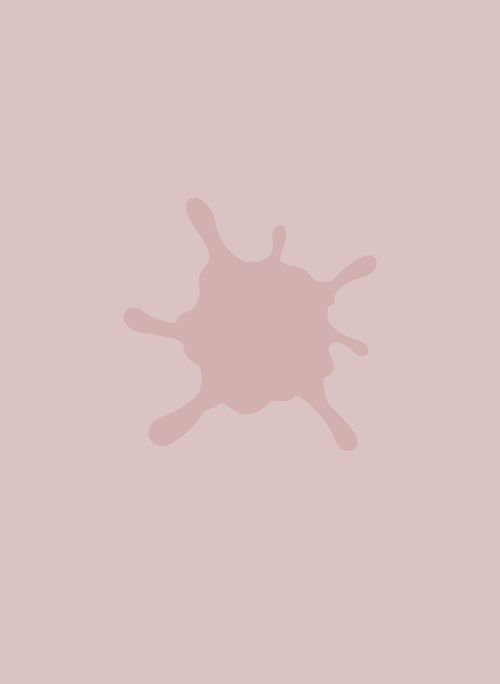わたしは精一杯の気持ちを取り繕う。
彼女は意味ありげな笑みを浮かべながらも、深くは追及しなかった。
「そういうならいいけど、小梅がこの前の日曜日、樹を見たんだって」
「へえ」
本当はいろいろ聞きたい気持ちがわいてくるが、そんな気持ちを押し殺し、淡々と返事をする。
彼女は手にしていたアイスを平らげ、立ち上がる。
「続きはないの?」
彼女は少し考えると、「ないよ」と口にし、プラスティックパックをゴミ箱に捨てると、部屋を出て行った。
樹は三時間ほどして家に帰ってきたようだ。
夕食時に顔を合わせた彼は、ここ最近通りの弟だ。
同時に今までずっと見知っていたはずの彼が、どことなく知らない人に見えたのだ。
彼女は意味ありげな笑みを浮かべながらも、深くは追及しなかった。
「そういうならいいけど、小梅がこの前の日曜日、樹を見たんだって」
「へえ」
本当はいろいろ聞きたい気持ちがわいてくるが、そんな気持ちを押し殺し、淡々と返事をする。
彼女は手にしていたアイスを平らげ、立ち上がる。
「続きはないの?」
彼女は少し考えると、「ないよ」と口にし、プラスティックパックをゴミ箱に捨てると、部屋を出て行った。
樹は三時間ほどして家に帰ってきたようだ。
夕食時に顔を合わせた彼は、ここ最近通りの弟だ。
同時に今までずっと見知っていたはずの彼が、どことなく知らない人に見えたのだ。