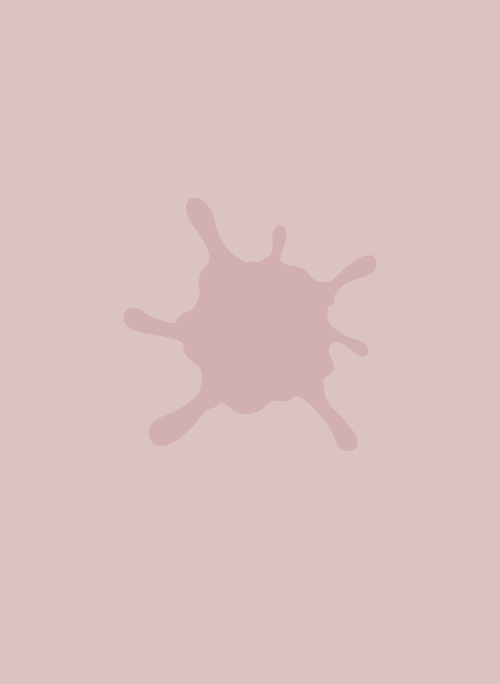「ゆっくり考えてね。わたしは焦らないし、気持ちが変わるのを待つよ。お姉さんもわたしたちのことを応援してくれるんだって」
彼女はそれだけを言い残すと、わたしに頭を下げる。彼女は踵を返し、立ち去っていく。
砂を踏む音が耳を掠めた。
顔をあげると、樹がまるでクラスメイトに向けているような他人行儀な笑みを浮かべていたのだ。
「帰ろうか。姉さん」
わたしはその言葉に唇を噛んだ。
わたしと樹はそのまま学校を出る。
樹は一言も口を開かなかった。
「樹、あのね」
数えきれないほど、言葉を飲み込んだ後やっとの思いで言葉を絞り出す。
「何も言わないでいいよ。俺たちは姉弟だもん」
だが、その振り絞った勇気も樹の言葉に一掃される。
彼はわたしを拒絶したのだと感じ取ったためだ。
家に帰ると、樹はそのまま直行して、わたしは玄関に取り残される。
わたしは玄関に座り込んだ。
彼女がわたしと樹とのキスを見ていたとして、樹とのことが知られればどうなるのだろう。
わたしだけならいい。樹まで変な目で見られるに決まっているのは絶対に嫌だった。
だから、わたしは彼女の言ったように邪魔だけはしないようにと心に誓った。
彼女はそれだけを言い残すと、わたしに頭を下げる。彼女は踵を返し、立ち去っていく。
砂を踏む音が耳を掠めた。
顔をあげると、樹がまるでクラスメイトに向けているような他人行儀な笑みを浮かべていたのだ。
「帰ろうか。姉さん」
わたしはその言葉に唇を噛んだ。
わたしと樹はそのまま学校を出る。
樹は一言も口を開かなかった。
「樹、あのね」
数えきれないほど、言葉を飲み込んだ後やっとの思いで言葉を絞り出す。
「何も言わないでいいよ。俺たちは姉弟だもん」
だが、その振り絞った勇気も樹の言葉に一掃される。
彼はわたしを拒絶したのだと感じ取ったためだ。
家に帰ると、樹はそのまま直行して、わたしは玄関に取り残される。
わたしは玄関に座り込んだ。
彼女がわたしと樹とのキスを見ていたとして、樹とのことが知られればどうなるのだろう。
わたしだけならいい。樹まで変な目で見られるに決まっているのは絶対に嫌だった。
だから、わたしは彼女の言ったように邪魔だけはしないようにと心に誓った。