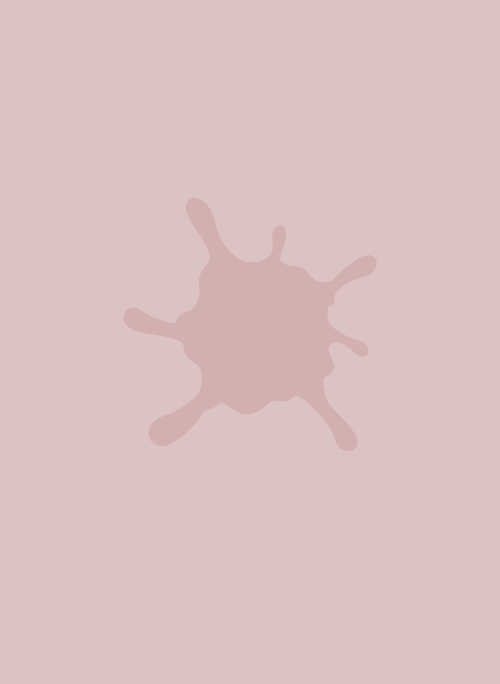「今日、千波のクラスメイトも一緒なんだよな。半田先輩も」
「部活があるから、遅くなると言っていたけど。会うのが嫌なら断るよ?」
「嫌じゃないかど、千波を誰にも見せたくない」
わたしは樹の発言の意図が分からず、首を傾げた。
別に樹の友人に見せるわけでもないため、彼が困る理由が分からない。
そもそも半田君とわたしは学校で頻繁に顔を合わせて居るため、会うのに躊躇するような仲でもない。
樹が会いたくないというなら、そういう言い方はしないはずだ。
樹はそこで黙ってしまっていた。
「飲み物でも買ってこようか?」
そう言い、立ち上がろうとしたわたしの手を樹が掴む。
「いらないの?」
わたしの問いかけにも、樹は無反応だ。
わたしも樹の発言の意図が見えてこず、何も言わずに彼の隣に座っておくことにした。
早送りをするかのように、徐々に辺りが暗くなっていく。それは花火の開始時間が迫っているということだ。
日和と別れて一時間以上は余裕で経過しているはずなのに、いまだに彼女からの連絡が届かない。
小梅ちゃんの家に言って、彼女の着付けを手伝っていたにしても時間がかかりすぎている。
念のためわたしは自由なほうの手で、電話をかけようとすると、樹が右手で制した。