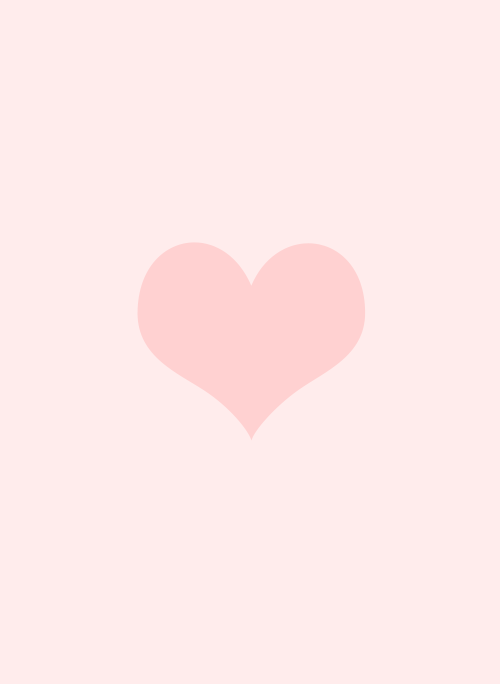それからと言うもの、私は図書室でも彼女のことを時々、目で追うようになった。
春瀬に気づかれない程度に。
そんなことどうでもいいじゃないか、とも思うけど。
それでも、気になるのだから仕方ない。
図書室での彼女はやはり、春瀬のことばかり見ていた。
………いや、訂正。
彼女は春瀬のことも見ていたけど、私のことも見ていた。
羨みの眼差しで。
恨み、ではなく、羨み。
時々、そんな彼女の視線と私の視線がぶつかるときもあった。
そんなとき。
彼女は必ず、私に向かって小さく笑顔を見せるのだ。
困ったような、悲しそうな。
本当は泣きたいのを我慢して無理矢理作ったような、崩れそうな笑顔。
私はどうしようもなくいたたまれなくなった。