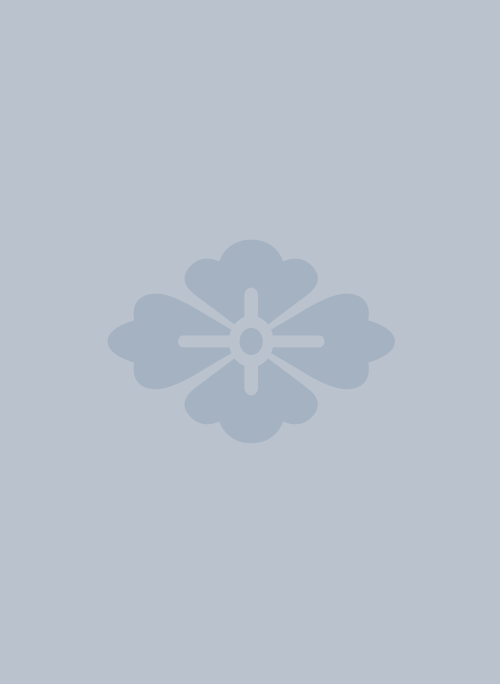「なら分かったわ。では太裳、玄武はこないようだから、二人で行きましょう?」
「太裳はワタクシを止めないでしょう」と太裳の手を取り、立ち上がる。
「そうね、別に聖凪の素性が知られようが、知られまいが、私には関係の無い事だもの。」
シレッと言ってのけた太裳に、流石に頭の血管が浮き出そうになった。
「…なら、行きましょう」と、外に出る支度を始めると、案の定玄武が怒り始めた。
少し見た目が冷たそうで、性格は落ち着いてはいるが何処か、大人気ない玄武だが、面倒見は良いのだろう。
「聖凪!!私は貴女の為を思って言っているのよ!?」
それは、分かってはいるけれど…アタシには時間が無いのだ。
お祖父様をはじめ、一族の方々には申し訳ないけれど、多少の無茶は仕方がないと思っている。
お父様や兄上や、陰陽寮の陰陽師たちがいる事は知っている、誰に命ぜられた訳でもない。
だけど、都を…この国を護るのだと、アタシは自分に誓ったんだ。
「ごめんなさい、玄武。今度ばかりは、何を言われても引き下がる訳には行かないの。」
アタシの本気が伝わるように、真っ直ぐに玄武の瞳を見つめる。
ジッと、アタシを見つめ返していた玄武が、目を閉じて深いため息をついた。
「…もう、分かったわよ。私がお供になろうじゃない…だけど、今回だけよ?」
「玄武っ」
玄武は、「まったく」と呆れていたけれど、直ぐにアタシの無理なお願いを聞いてくれるようだ。
「ありがとう!!」
アタシは太裳と目を合わせて、ニッとお互いに微笑み合う。
「何かしら、その合図は?」
う"…
恐ろしい。