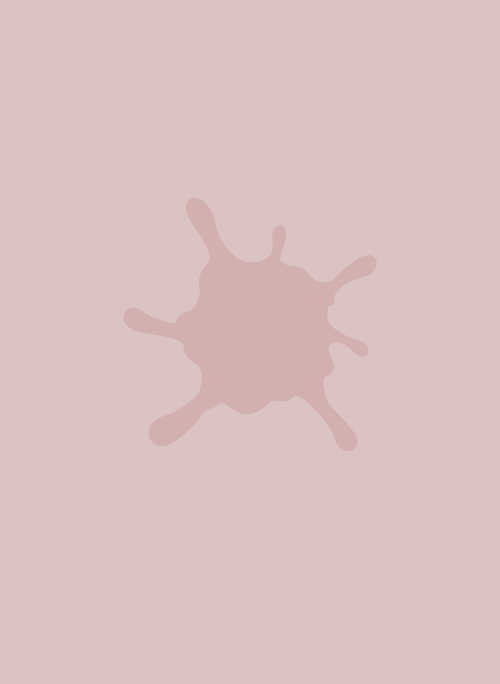小さい頃の拓馬は泣き虫で、よく泣いていた。
わたしはそんな拓馬の世話をかいがいしくしていた気がする。
それは泣いていた彼が心配だったからという単純なものだった。
「今日は元気ないね」
拓馬はわたしの顔を覗き込んできた。
綺麗な顔が視野に収まり、意図しないうちに心臓の鼓動が乱れていた。
目をそらし、そんな心臓の鼓動に気づかない振りをした。
「昨日、寝不足だっただけ」
受験勉強でと言えれば受験生らしくていい。
だが、実情は違っていた。家に帰ってから拓馬とあの名前も知らない少女がかなしそうにしたのが頭から離れなかったのだ。
ベッドに入ってもそのことを思い出し、寝るのを諦めた夜中の三時過ぎにやっと眠ることができたのだ。
「勉強もいいけど、体調を崩さないようにね」
そうさらっと言葉が出てくる。拓馬にとってのわたしのイメージはそうなのだろう。
わたしはあいまいに頷く。
わたしの思考はどちらかと言えば単純で、あまり物事に思い悩むということはなかった。
それどころか泣いた記憶もあまりない。
わたしはそんな拓馬の世話をかいがいしくしていた気がする。
それは泣いていた彼が心配だったからという単純なものだった。
「今日は元気ないね」
拓馬はわたしの顔を覗き込んできた。
綺麗な顔が視野に収まり、意図しないうちに心臓の鼓動が乱れていた。
目をそらし、そんな心臓の鼓動に気づかない振りをした。
「昨日、寝不足だっただけ」
受験勉強でと言えれば受験生らしくていい。
だが、実情は違っていた。家に帰ってから拓馬とあの名前も知らない少女がかなしそうにしたのが頭から離れなかったのだ。
ベッドに入ってもそのことを思い出し、寝るのを諦めた夜中の三時過ぎにやっと眠ることができたのだ。
「勉強もいいけど、体調を崩さないようにね」
そうさらっと言葉が出てくる。拓馬にとってのわたしのイメージはそうなのだろう。
わたしはあいまいに頷く。
わたしの思考はどちらかと言えば単純で、あまり物事に思い悩むということはなかった。
それどころか泣いた記憶もあまりない。