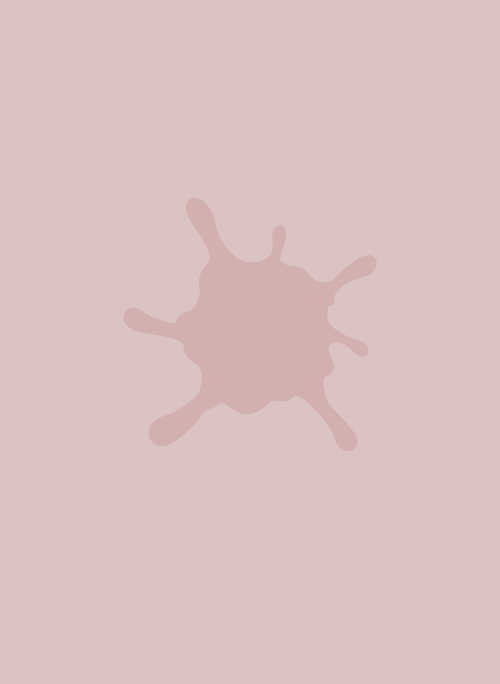奈月は得意げにさらりとかわす。
彼女は汚いといった言葉を否定するつもりはないようだった。
素直に低くなったといえばいいのに、わざとなのだろう。
口先が達者な彼女がそんな言葉を知らないとは思えなかった。
「じゃ、行こうか」
腕を引かれ、拓馬を見る。彼の行動で我に帰る。
「どこに行くのよ。手を離しなさいよ」
「美月のおじさんとおばさんに呼ばれていてさ」
「そんなの聞いてない」
「だって言わないように頼んでおいたから。サプライズって感じでいいでしょう? きっと脳が刺激を受けて活性化するよ。受験勉強で四苦八苦しているお姉ちゃんへの贈り物よ」
奈月は屁理屈としか思えないことを言い出していた。
彼女の瞳はさっきとは異なり興味の対象を見つけた子供のように輝いている。
このまま家に帰りたくなかったわたしは適当な理由を作り出した。
「わたし、寄るところあるの」
「お母さんがケーキを買っていると言っていたけど、お姉ちゃんの分も食べていい? お姉ちゃんの大好きなチョコレートケーキ」
その言葉でわたしの動きが止まる。
食べ物の名前に露骨に反応してしまう自分が情けない。
彼女は汚いといった言葉を否定するつもりはないようだった。
素直に低くなったといえばいいのに、わざとなのだろう。
口先が達者な彼女がそんな言葉を知らないとは思えなかった。
「じゃ、行こうか」
腕を引かれ、拓馬を見る。彼の行動で我に帰る。
「どこに行くのよ。手を離しなさいよ」
「美月のおじさんとおばさんに呼ばれていてさ」
「そんなの聞いてない」
「だって言わないように頼んでおいたから。サプライズって感じでいいでしょう? きっと脳が刺激を受けて活性化するよ。受験勉強で四苦八苦しているお姉ちゃんへの贈り物よ」
奈月は屁理屈としか思えないことを言い出していた。
彼女の瞳はさっきとは異なり興味の対象を見つけた子供のように輝いている。
このまま家に帰りたくなかったわたしは適当な理由を作り出した。
「わたし、寄るところあるの」
「お母さんがケーキを買っていると言っていたけど、お姉ちゃんの分も食べていい? お姉ちゃんの大好きなチョコレートケーキ」
その言葉でわたしの動きが止まる。
食べ物の名前に露骨に反応してしまう自分が情けない。