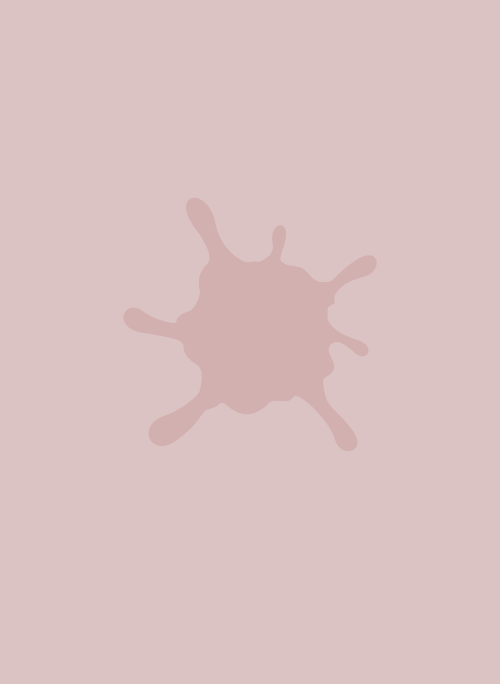「教えてくれれば見舞いに来たのに」
「美月には見られたくなかったから」
「どうして?」
「なんかかっこ悪いし」
わたしは彼の言葉に思わず笑ってしまっていた。
かっこいいとかかっこ悪いとかそんな問題でもない気がしたからだ。
複雑だった気持ちがすっと楽になっていく。
「幼馴染なんだからそんなの気にしなくても」
「戻ってきたら美月にだけはかっこ悪いところを見せないようにしようと思っていたから」
「どうして」
答えは半分は分かっていたのかもしれない。だが、わたしには実感がなかった。
わたしと彼はつりあわない。彼はその容姿がどれほど人を引き付けるのか理解しておらず、幼いころの幻想に取りつかれているだけなのかもしれない。
どれほど自分を過大評価しようとも彼とつりあうという結論には至らなかったのだ。
その彼の目が大きく見開かれた。
わたしはその後姿を目で追う。
肌の色が通るような白さの、少し釣り目の少女が立っていた。
彼女は一瞬、卑屈な笑みを浮かべると、鍵を閉め、拓馬の傍に駆け寄る。
「美月には見られたくなかったから」
「どうして?」
「なんかかっこ悪いし」
わたしは彼の言葉に思わず笑ってしまっていた。
かっこいいとかかっこ悪いとかそんな問題でもない気がしたからだ。
複雑だった気持ちがすっと楽になっていく。
「幼馴染なんだからそんなの気にしなくても」
「戻ってきたら美月にだけはかっこ悪いところを見せないようにしようと思っていたから」
「どうして」
答えは半分は分かっていたのかもしれない。だが、わたしには実感がなかった。
わたしと彼はつりあわない。彼はその容姿がどれほど人を引き付けるのか理解しておらず、幼いころの幻想に取りつかれているだけなのかもしれない。
どれほど自分を過大評価しようとも彼とつりあうという結論には至らなかったのだ。
その彼の目が大きく見開かれた。
わたしはその後姿を目で追う。
肌の色が通るような白さの、少し釣り目の少女が立っていた。
彼女は一瞬、卑屈な笑みを浮かべると、鍵を閉め、拓馬の傍に駆け寄る。