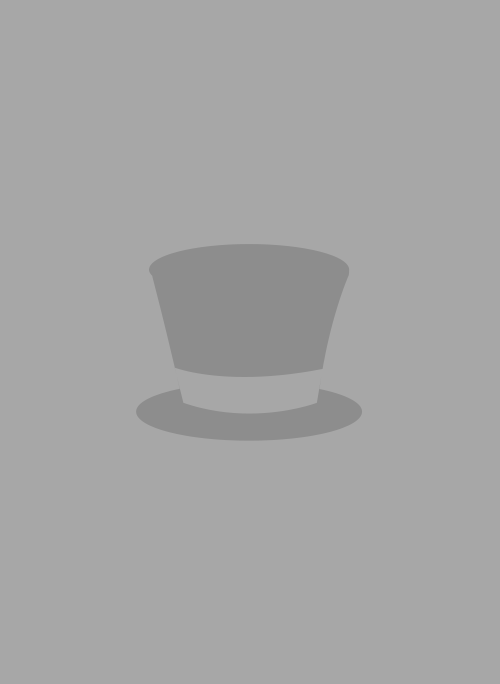午前中の授業が終わり椋は購買で買ったパンを持って屋上に上がった。
死んだ者が現れた日は、一人で屋上に上がるのが決まりになっていた。
殆どの死んだ者は僕の後をついて来る。
しかも朝出会った死んだ者は、決まってこの昼休みにやって来る。
きっと整理するのに、それだけの時間がいるのかもしれない。
「椋くん…。」
椋が屋上で寝転んでると村木が話しかけて来た。
「はい。」
「娘は今お腹に赤ちゃんがいるんだ。」
さすがの椋もこの言葉に驚いたのか、飛び起きた。
「それなのに死んだんですか?!」
「いや、きっと娘は僕の事は知らない。」
村木は悲しげな目をした。
「知らない?」
「うん、娘が幼い時に離婚して、前妻はすぐに再婚したんだ。娘は再婚相手を実の父親だと思ってるからね…。」
「じゃなんで娘さんが妊娠中ってこと知ってるんです?」
「前妻に聞いたんだ…偶然街で会ってね…。」
「じゃ娘さんも村木さんの事知ってるんじゃ?」
「ううん。それはない。前妻は言ってないと言っていたし、私も言わない方がいいと思ったからね。」
「じゃなんで気になるんです?」
「あの子が私の事を知らなくても私にとっては娘であって、産まれてくるのは私の孫だ。」
「じゃ村木さんの未練は?」
「一目でいい…娘と孫の顔が見たいんだ。」
椋は一息つくと立ち上がり、ついた汚れをはらうと村木に言った。
「わかりました。じゃその娘に会いにいきましょう。」
「会いに?」
「はい。あっでも今からじゃないですよ。僕は午後からも授業がありますから…二時間後、校門で待ってて下さい。」
「うん。わかったよ。」
「じゃ。教室戻ります。」
椋は村木をその場に残し階段を下りて行く。
教室に入る手前で声を掛けられた。
「椋、終わったの?」
「うん。放課後ちょっと行ってくる。」
「手伝うことある?」
「いや、今のところ何もないかな。」
「そっか、気をつけてね。」
「うん、ありがとう。」
午後の授業の始まりを告げるチャイムが鳴り響く。
二人はそれぞれの教室に戻った。
この学校で僕の事を知っているのは、幼馴染である彼女だけだ。
世良しずくはこの世でただ一人の理解者だ。
しずくは見えない普通の人間なのに、何故か僕の事を信じている。
しかも、僕から打ち明けたのではない。
ある日突然聞いてきた。
「椋って幽霊見えてるよね!」って。
あまりにも急に、それでいて的確に言われ僕は素直に「うん。」と、答えてしまった。
それが小学生の三年生だった。
それからもう5年になるけれど、しずくは変わらず接してくれている。
死んだ者が現れた日は、一人で屋上に上がるのが決まりになっていた。
殆どの死んだ者は僕の後をついて来る。
しかも朝出会った死んだ者は、決まってこの昼休みにやって来る。
きっと整理するのに、それだけの時間がいるのかもしれない。
「椋くん…。」
椋が屋上で寝転んでると村木が話しかけて来た。
「はい。」
「娘は今お腹に赤ちゃんがいるんだ。」
さすがの椋もこの言葉に驚いたのか、飛び起きた。
「それなのに死んだんですか?!」
「いや、きっと娘は僕の事は知らない。」
村木は悲しげな目をした。
「知らない?」
「うん、娘が幼い時に離婚して、前妻はすぐに再婚したんだ。娘は再婚相手を実の父親だと思ってるからね…。」
「じゃなんで娘さんが妊娠中ってこと知ってるんです?」
「前妻に聞いたんだ…偶然街で会ってね…。」
「じゃ娘さんも村木さんの事知ってるんじゃ?」
「ううん。それはない。前妻は言ってないと言っていたし、私も言わない方がいいと思ったからね。」
「じゃなんで気になるんです?」
「あの子が私の事を知らなくても私にとっては娘であって、産まれてくるのは私の孫だ。」
「じゃ村木さんの未練は?」
「一目でいい…娘と孫の顔が見たいんだ。」
椋は一息つくと立ち上がり、ついた汚れをはらうと村木に言った。
「わかりました。じゃその娘に会いにいきましょう。」
「会いに?」
「はい。あっでも今からじゃないですよ。僕は午後からも授業がありますから…二時間後、校門で待ってて下さい。」
「うん。わかったよ。」
「じゃ。教室戻ります。」
椋は村木をその場に残し階段を下りて行く。
教室に入る手前で声を掛けられた。
「椋、終わったの?」
「うん。放課後ちょっと行ってくる。」
「手伝うことある?」
「いや、今のところ何もないかな。」
「そっか、気をつけてね。」
「うん、ありがとう。」
午後の授業の始まりを告げるチャイムが鳴り響く。
二人はそれぞれの教室に戻った。
この学校で僕の事を知っているのは、幼馴染である彼女だけだ。
世良しずくはこの世でただ一人の理解者だ。
しずくは見えない普通の人間なのに、何故か僕の事を信じている。
しかも、僕から打ち明けたのではない。
ある日突然聞いてきた。
「椋って幽霊見えてるよね!」って。
あまりにも急に、それでいて的確に言われ僕は素直に「うん。」と、答えてしまった。
それが小学生の三年生だった。
それからもう5年になるけれど、しずくは変わらず接してくれている。