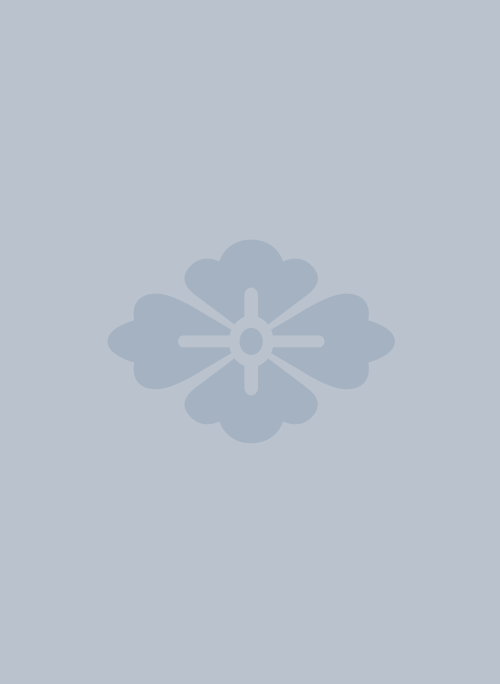「雪……
雪……?
大丈夫……?」
愛しい声に呼ばれて、目が覚めれば。
そこは、由香里の病室だった。
どうやら、オレは。
見舞いの最中に、由香里のベッドに突っ伏したまま。
疲れ果てて、眠っていたらしい。
「さすがの雪も、大学の勉強は、難しい?
夜遅くまで、勉強しているのかな……?」
ベッドにアタマを預けたままの、オレの髪を撫でながら。
由香里は、何も知らずに、微笑んだ。
その手は、悲しいほどに、痩せさらばえて。
打たれ続ける、点滴の跡が痛々しかった。
優しい言葉が紡がれる口には、もう酸素マスクが、欠かせずに。
毎日、毎日、由香里のキレイな顔を、半分も隠していた。
……もう、耳を澄まさなくても。
……音が、聞こえる。
由香里の命の砂が、こぼれて落ちて。
……消えてゆく、音が。