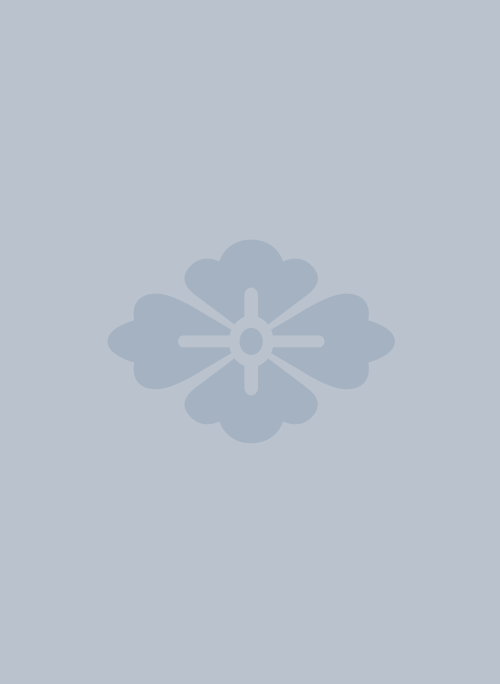「ねぇ、きみ!
大丈夫……?
生きてる、わよね?」
アルトよりも、更に低く、かすれた。
それでも、艶っぽい声に顔を上げると。
髪の長い女が、オレの顔を覗き込んでいた。
胸の大きな見事なカラダを、高価そうな毛皮でくるんで。
片手に、ブランドものの傘を差し、もう片方の手をひざに当てて小首を傾げている。
いかにも、夜に生きる女らしく。
辺りが暗くても、化粧が厚いのが、よくわかる。
その素顔がどうか、なんて、判るはずもないけれども。
しぐさを見れば。
とても可愛い、感じのする女だった。
「きみ!
酔っ払って動けないの?
こんなトコロで眠ると、凍死するわよ!?
マジで」
……凍死!
見ず知らずのあんたが、凍死、なんて言うのか!?
心配そうな女の言葉が、妙に笑えた。
「……凍死、なんてしねぇよ。
山の中じゃあるまいし」
本当は、ゲラゲラ笑いたいのに、力が出ず。
喉の奥でくっく、と笑ってクビが少しのけぞれば。
オレのアタマに降り積もった雪が。
とさとさっ、と軽い音をたてて落ちてゆく。