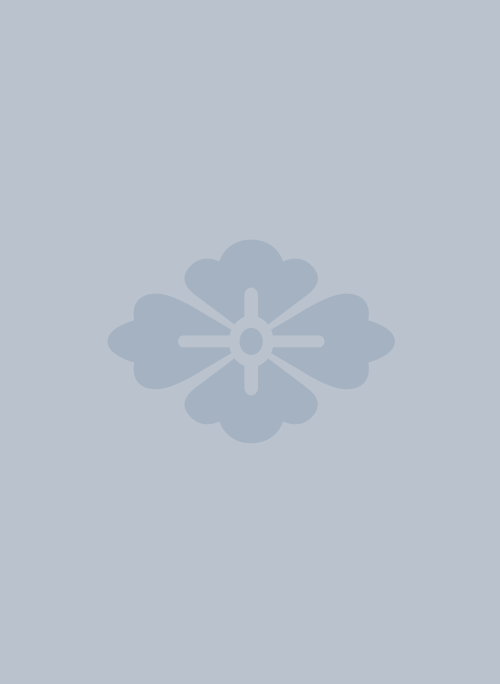「……一緒に帰ってあげたら?」
「由香里」
……お前は。
……お前が。
この。
いかにも何か、たくらんでいそうなアヤネの、肩を持つのか?
女の考えていることは、わからねぇ。
複雑な気分で由香里を見れば。
やっぱり、由香里も、ちょっと困った顔をして、肩をすくめた。
「アヤネさん、きっと。
どうしても雪に、話たいことでもあるんじゃない……?」
思いもかけない由香里の言葉に。
アヤネは一瞬息を呑んで。
ふ、ふん、と鼻を鳴らした。
「なによ!
ようやく、アナタにも。
遠慮って言葉が、わかって来たみたいよねっ!
そんな変な形のケーキしか食べられない貧乏人のクセに!」
……変な形って、お前。
「……そのケーキは、オレがはじめて作ったケ―キなんだけど」
「ええっ!
ウソ!
音雪のケ―キだったの!?」
「そうだ。
変なケ―キで悪かったな!」
自然と不機嫌になる口調に、アヤネは、驚いて言った。
「なんで、音雪のケ―キをその子が食べてるのよ!
ケ―キは、本当は私のモノよね!?」