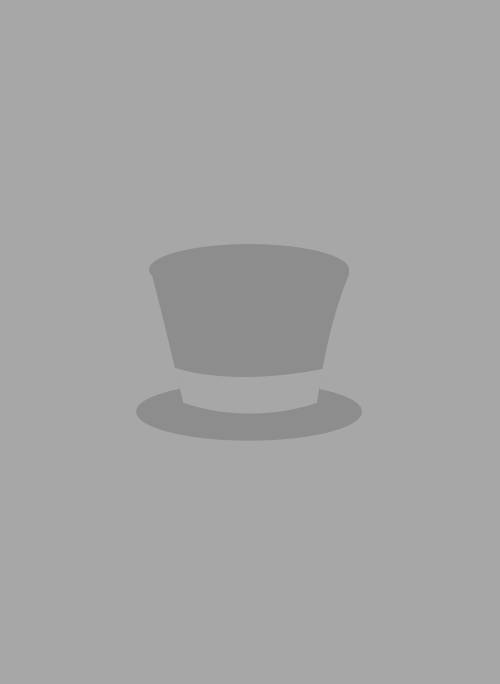『まもなくー、3番線、7時56分発、天針(てんはり)行きの電車が参りますー、危ないですから、黄色い線の内側に―――』
ガタンガタン……ガタンガタン……ゴトン……ガタンガタン……
駅のホームを通る風が髪をかき乱す。
夏の夜はかき氷の冷気のようにキンと冷える。
時音は捲っていた服の袖を直した。
「えーっと、鞄持った、定期券はチャージした、お土産も持った、今度は時音は迷子になってない。よし、忘れ物は無いわね?」
「忘れ物じゃないけど……心配だな」
「それ、両方の事言ってる?きっと、帰ってくるわよ。時音の記憶も、そのうちいずれ戻るでしょ」
まだぽわんとしてる頭で、申し訳なく思った。
あれからの記憶が一部飛んでいる。
この二人が両親である事も、ついさっき思い出した。
頭の中がスポンジケーキのように隙間だらけで軽くなったような、大事な事だけすっぽ抜けてるような感覚があった。
夏祭りへ行ったのはなんとか思い出せた。
だがそこから何をして誰とあったのか、全く覚えてない。
「とっきー!!」
犬の遠吠えのような大声が近づいてきた。
振り返ると、息を切らしながらランニングシャツに短パン姿の少年がこっちをじっと見てる。