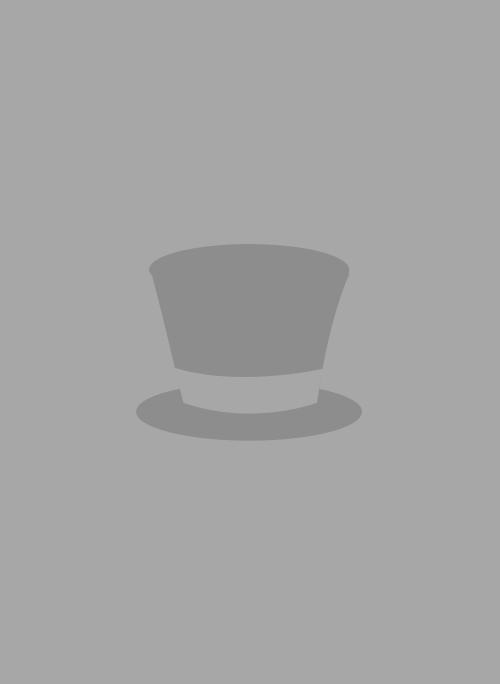新学期が始まったら、また学校があるT県に戻らなくてはいけない。
それは、少年と離れてしまう事でもあった。
手紙のやりとりをしようにも、まだ小学生の時音には住所も郵便番号も覚えられない。
会いに行きたくても、電車と飛行機に乗るからお金も時間もかかる。
この夏祭りが終わった次の日、真夜中の電車に乗る。彼とはこの夏祭りが終わったらサヨナラしなくてはならない。
「もう私達、会えないかもしれない……」
そう思うと、涙がどんどん溢れてきた。
迷子だった自分を元気づけてくれた彼。
こっちじゃ友達がいなくて毎年退屈していた自分と友達になってくれた彼。
あだ名をつけて、楽しそうに何度も呼んでくれる彼。
明日になれば、全部なくなる。
離れた所で鳴ってる笛の音が、余計に虚しさを駆り立てた。
「……どこに行ったって、俺が見つけてやる!」
照れ隠しなのか、少年はいつも斜めがけしてる狐面を正面にかけ直すと、そう宣言した。
握った手に力が籠るところから、本当は彼も離れたくないのが伝わってくる。
「だって……おめーが好きだし」
「……え」
狐面の隙間から見える頬が赤いのは、提灯の明かりのせいだけじゃない。