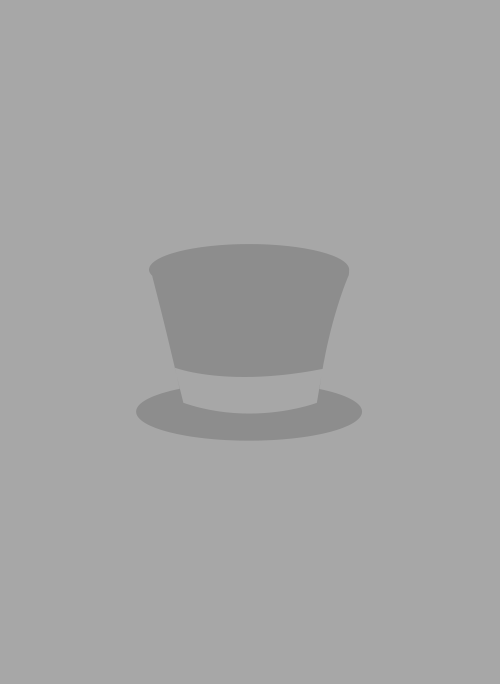「はぁ……」
鳥居には着いたものの、人気が無い上に祭の灯りが届かず暗く、何だか怖い。
このまま迎えが来なかったらどうしよう。
ばあちゃん家どころか、実家であるT県に帰れなかったらどうしよう。
朱色の前掛けを付けた狐の像が『この弱虫娘め』と馬鹿にしてるように見えて、少女はまた泣きそうになった。
「何お前、迷子?」
「きゃっ」
狐のお面を斜めがけした少年が突然現れた。
祭りの灯りの逆光で顔がはっきり見えないが、少女と歳はそんなに変わらないだろうか。
「なっさけねーなぁ。迷子で泣いてんのかよ」
「んなっ、泣いてないもん!泣いてないしっ」
浴衣の袖で乱暴に目元を擦り、頬を膨らませる。
でも少年は馬鹿にしたような笑みを浮かべると、ずいっと手に持っていたものを差し出した。
「ほら、これやるよ。せっかくの祭りなのに涙で視界が滲んでたら、もったいないぞ」
それは祭りの提灯で光るりんご飴だった。
「……きれい」
「だろー?屋台のおっちゃんが、おまけしてくれたんだ。食ってみろよ。丸かじりして食うんだぜ」