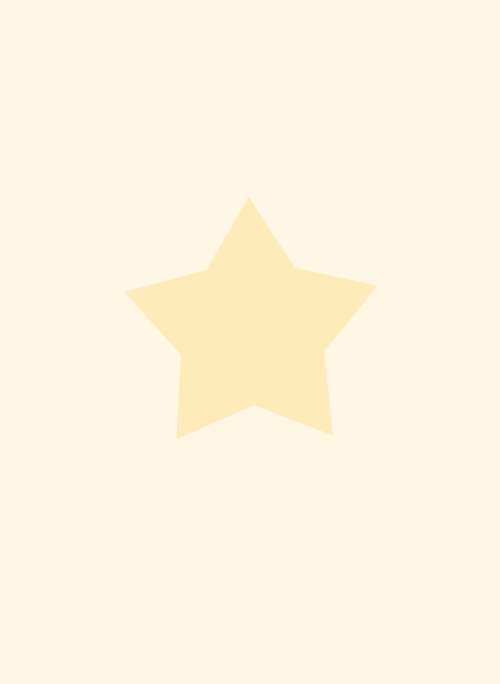一般「君、大丈夫かい?」
たった一言、そう声を掛けられただけで、私の中の何かがプツンと切れたがした。
希輝「…ぅ……ぁああああああああああっ、!!」
いきなり泣き崩れて叫び出した私に、声を掛けたおばさんも、周りの野次馬も、酷く驚いただろう。
けど、そんなことを構っている余裕なんか一切なかった。
私の中の'何か'が全て雪崩のように崩れ、崩壊してしまっていた。
3人の『死』をこの目で見てから、きっと私の中の'何か'は壊れていたんだ。
希輝「……ぁあぁぁあぁぁっ、!!
ぱぁぱー!!まぁまー!!
やだあぁぁぁぁぁあ…っ……ぅぁぁぁあぁっ!!」
そのまま私はただただ泣き叫んだ。
ピーポーピーポーとどこか遠くから聞こえてきた様な気がしたが、その頃にはもう頭の中はモヤに包まれていて何も認識出来なかった。
誰かが必死に私を宥めて、呼び掛けていたのを意識のどこかで聞いたような気もしたが、何も答えることのないまま意識を失った。
…そして、私が目を覚ましたのは事故から丸一日経ってからだったという。
目覚めた私の傍にいたのは、パパでもママでも来蘭でもお兄ちゃんでも百桃でもなかった。
辰巳「……キィ」
おじいちゃんだった。
希輝「……お、じいちゃん……?どー、、した…の…?」
深い眠りから覚めたばかりで気絶する直前のことを思い出してはいなかった。
ただ、どうしておじいちゃんが私を抱きしめているのかがわからなかった。
希輝「…ね、………ららは、?」
気絶する直前にあれだけ叫んだからか声は掠れて、絞り出すように問いかけた。
それが、どれだけ残酷なことだとは認識せずに。
いつもより回転の鈍い頭で、ふと思いついたことをただ口に出した。
希輝「……ぱ、ぱ……?っ………まま、は…?」
けれど、口に出していく中でどんどんと記憶が浮き上がってきた。
パパの動かない血塗れの体。
酷く冷たかったママの顔。
何かもわからない状態だった来蘭。
煙の上がったあの現場。
全てが瞳に焼き付いていた。
希輝「ぁ……ぁあっ……………ぱぱ…っ、ままっ………ららぁっ……!…、ぅぁぁあぁ……っ!!」
フラッシュバックし、酷く取り乱した。
頭を抱えて叫び出した私をおじいちゃんはただ抱きしめていた。