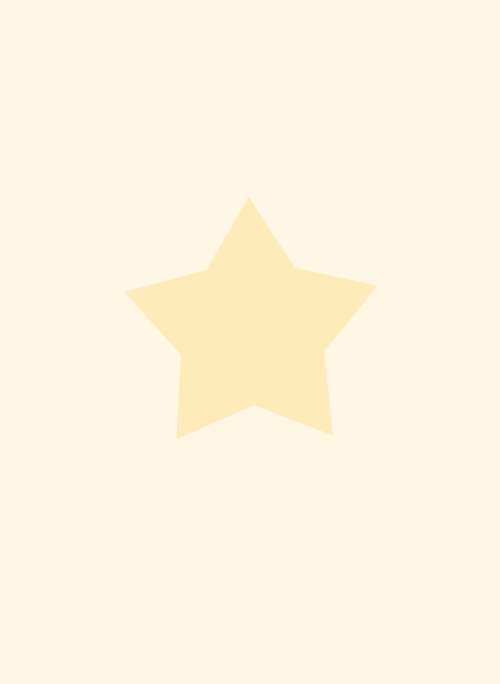「なんでそんなこというの!?
僕にはにいちゃんなんていない!!僕はっ!」
「いるんだよ、神楽。
だって、僕が君のお兄ちゃんを殺したんだから」
「……は?」
やけに大人びた声色をした女の子は赤と銀に光る瞳で俺の目をじーっと見つめていた。
「ボクが、時雨をコロシたんだ」
プッツンーー
「……兄ちゃん…、コロシタ…?あんたが、、??うそだ」
一気に頭の中に火事の光景が吹き上がり、全てのことを思い出した瞬間だった。
「…ゴメンナサイ、ごめ」
「なんであやまってんの?
兄ちゃんは??あにきは??ねえ!どこなのさ!!」
女の子の謝罪を遮り、俺は夜中だということを忘れて怒鳴り散らした。
「ごめんなさ、」
「なあ!
あんたがあやまったら兄ちゃんはかえってくるの!?
兄ちゃんをころしたなら!!なんで俺の前にあらわれた!!
俺にころしてほしいのかよ!?兄ちゃんを、かえしてくれるのかよ!」
吹き返した感情はもう、自分では止められないくらい高まっていた。
目の前の女の子が誰だかも知らないのに。
言ってることが本当かどうかなんて確認しようが無いのに。
ただ目の前の同じくらいの子供が、兄ちゃんを殺したということが許せなかった。
「兄ちゃんをかえせっ!!」
ただあの火事のせいで、この女の子のせいで、兄ちゃんが死んだということだけが俺の頭を支配していた。
「…あの、コレ…、」
バシッ
「ふざけんな!!
こんなもので兄ちゃんのかわりになるとでもいうの!?」
「ちがっ!」
片言になりかかっていた言葉は普通に戻り、その声色は年相応だった。