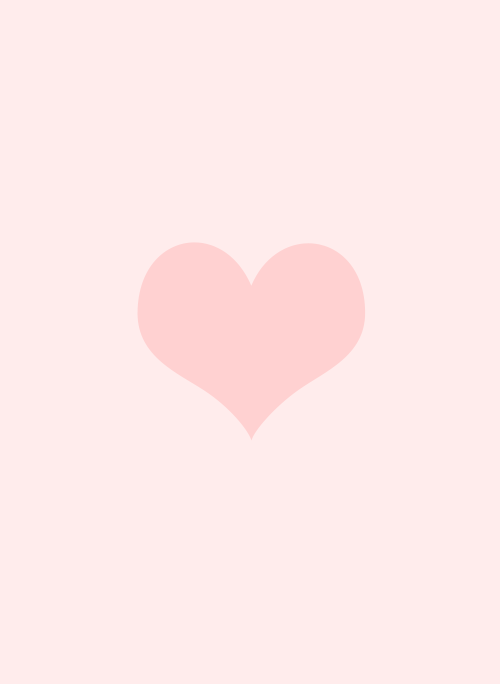もちろん、俺は戸惑っていた。
声優という仕事のことは、まるで意識したことがなかったからだ。
一方で、自分の特長が声であると、プロから指摘されたことが驚きであり、喜びでもあった。
プロが魅力的だと言ってくれているのだから、その道にチャレンジしてみれば、何か新しい道が拓けるかもしれない。
何より、身長やルックスを気にすることなく、演技を続けていけるというのが魅力的だった。
「……やります。やらせてください。」
しばらくの逡巡の後、俺は林さんに頭を下げていた。
これが、俺の何度目かの運命の分岐点だった。
声優という仕事のことは、まるで意識したことがなかったからだ。
一方で、自分の特長が声であると、プロから指摘されたことが驚きであり、喜びでもあった。
プロが魅力的だと言ってくれているのだから、その道にチャレンジしてみれば、何か新しい道が拓けるかもしれない。
何より、身長やルックスを気にすることなく、演技を続けていけるというのが魅力的だった。
「……やります。やらせてください。」
しばらくの逡巡の後、俺は林さんに頭を下げていた。
これが、俺の何度目かの運命の分岐点だった。