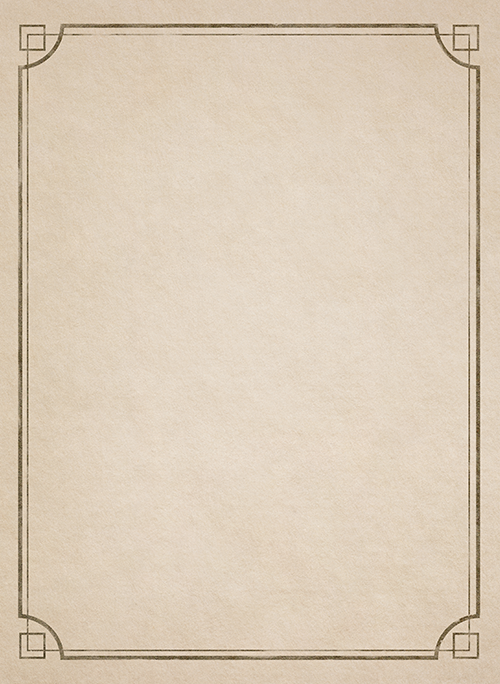「すべて無駄だった」
その瞬間、全てを憎んだ。
なんで呼び出しに応じたんだろうと自分の馬鹿さ加減に吐き気がした。
今日は満天の夜空で、こんな日に彼と会えることの素晴らしさに歓喜し、新品のスカートをはいた。
彼の褒めてくれた少し高めのヒールも、勝負の日につける赤い口紅も、すべて無駄になったと頭の端で思った。
目に涙をためて俯く彼は、私が目の前に座っても顔を上げない。
「僕は無力なんだ、わかっていた…彼の苦しみを知っていてなんにも…」
膝の上で握った手に、爪が食い込んでいる。
痛いでしょ?やめてよと言いたいけど言えない。
騒がしいファミレスの店内で、彼といるこの空間だけ切り離された様に重く静かだった。
会えば必ず目を見て笑ってくれる彼の優しい声は震えていた。
意志の強い瞳は伏せられ、私を見ることもない。
長い指は結ばれ固く閉じられている。
その全てで、彼は私を見ていないことに気づかされた。