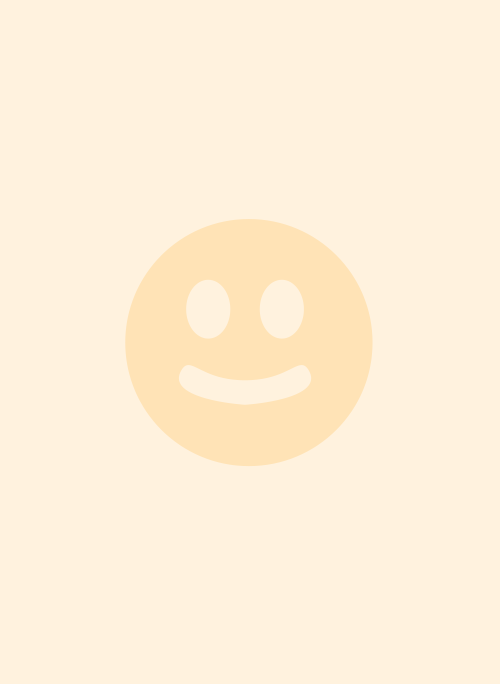「なに、これ……」
理科室の流しにおいてあったバケツには、白く泡が濁ったシャツがあるはずなのに。
その場は清潔感あふれる洗剤の匂いではなく、深く濃い茶色の香ばしい香りでかき消されていた。
隣にいたミカドも驚いていたようだった。
そっと手に取ってみると、まっ白だったはずのシャツが、コーヒーによって違う薄い黄色に染められていた。
「…あ…、あの、ごめんなさい……」
あたしは頭を下げたけど、無言でミカドはまだ濡れたままの上質なシャツに長い指が触れた。
その静かな空間が、あたしの無責任さを責め立てるようで苦しい。
なんでこうなったの?誰がこんなことを?
たくさんの疑問はあるものの、申し訳なさで声がうまく出ない。
こんなんじゃ、問答無用で生涯使用人、なんて命令されてもいた仕方ない。
けど、俯いたあたしの耳に届いたのは、ミカドの罵声でも憤慨の様子でもなかった。
ピ、ピ。
小さなタッチ音のあと、すぐに電子音が静かな理科室に響いた。
「あー、もしもし、禅?代替のシャツってあったっけ…?」
あくまでも冷静なミカドの声。
顔を上げると、まるでなんにもなかったような表情で、耳に最新の携帯電話をあてていた。
「あ、あの……!」
せっかく絞り出したあたしの声は邪魔といいたげに手をしっしと振られ、しぶしぶきゅっと口を結ぶ。
「なんでもいい、俺を誰だと思ってんだよ」
それは電話の向こうにいる禅くんにあてたものか、それとも目の前にいるあたしへのものか。
魅惑的な黒い瞳を細めたミカドは、自信過剰に言い放つ。
けれど、今のあたしには安心するかのような言葉に聞こえた。
二人きりの理科室に、静かな宣戦布告の鐘がなった。
.
理科室の流しにおいてあったバケツには、白く泡が濁ったシャツがあるはずなのに。
その場は清潔感あふれる洗剤の匂いではなく、深く濃い茶色の香ばしい香りでかき消されていた。
隣にいたミカドも驚いていたようだった。
そっと手に取ってみると、まっ白だったはずのシャツが、コーヒーによって違う薄い黄色に染められていた。
「…あ…、あの、ごめんなさい……」
あたしは頭を下げたけど、無言でミカドはまだ濡れたままの上質なシャツに長い指が触れた。
その静かな空間が、あたしの無責任さを責め立てるようで苦しい。
なんでこうなったの?誰がこんなことを?
たくさんの疑問はあるものの、申し訳なさで声がうまく出ない。
こんなんじゃ、問答無用で生涯使用人、なんて命令されてもいた仕方ない。
けど、俯いたあたしの耳に届いたのは、ミカドの罵声でも憤慨の様子でもなかった。
ピ、ピ。
小さなタッチ音のあと、すぐに電子音が静かな理科室に響いた。
「あー、もしもし、禅?代替のシャツってあったっけ…?」
あくまでも冷静なミカドの声。
顔を上げると、まるでなんにもなかったような表情で、耳に最新の携帯電話をあてていた。
「あ、あの……!」
せっかく絞り出したあたしの声は邪魔といいたげに手をしっしと振られ、しぶしぶきゅっと口を結ぶ。
「なんでもいい、俺を誰だと思ってんだよ」
それは電話の向こうにいる禅くんにあてたものか、それとも目の前にいるあたしへのものか。
魅惑的な黒い瞳を細めたミカドは、自信過剰に言い放つ。
けれど、今のあたしには安心するかのような言葉に聞こえた。
二人きりの理科室に、静かな宣戦布告の鐘がなった。
.