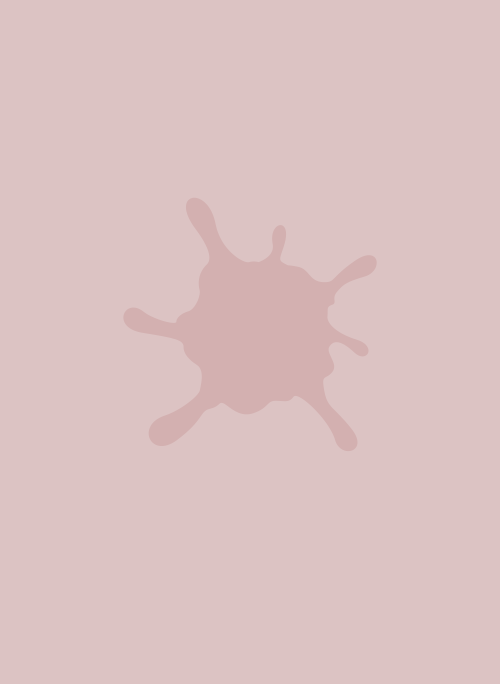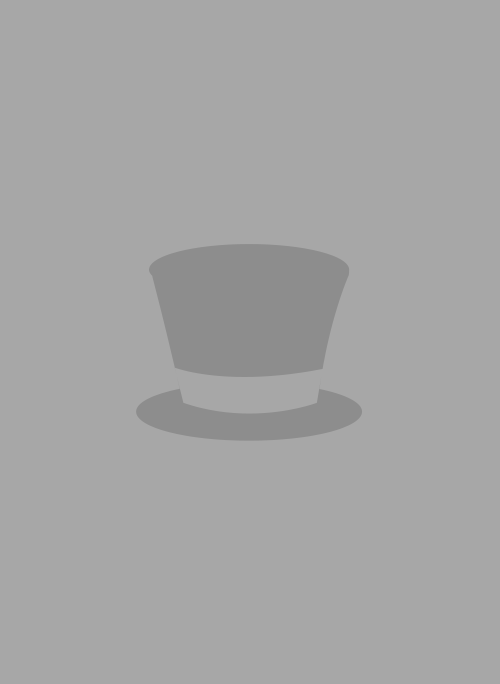階段を下り店の扉を開けて中に入ると、カウンターの内側に置いてある丸椅子にドカと腰を下ろす。
そして腹の底から吐き出す様に大きく溜め息を吐き、何度も首を横に振った。
「ああ・・・なぜ、俺の誘いを断るんだ?
カウンターのショーケースに並べてある指輪ですら、こんなに光り輝いているのに」
俺の指輪は、これだけでも十分に美しいが、理想的な指に嵌まってこそ究極の美に近付く。
理想的な指に――
俺は膝に手を当ててグイっと立ち上がると、そのまま作業場の扉を開いた。
照明を点けた瞬間、圧倒的な存在感を示す指輪達に俺でさえも気圧される。凛としてどんなものにも媚びる事もなく、燦然とオーラを放っている。
そうだ・・・そうなんだ。
俺が頭を下げる必要など、この指輪達には必要ない。愚かな女共に、この高貴な指輪達の価値が分かるはずがないのだから。
どうすれば良い?
俺の安易な行為で、この指輪達の品格を下げないようにしなければならない。