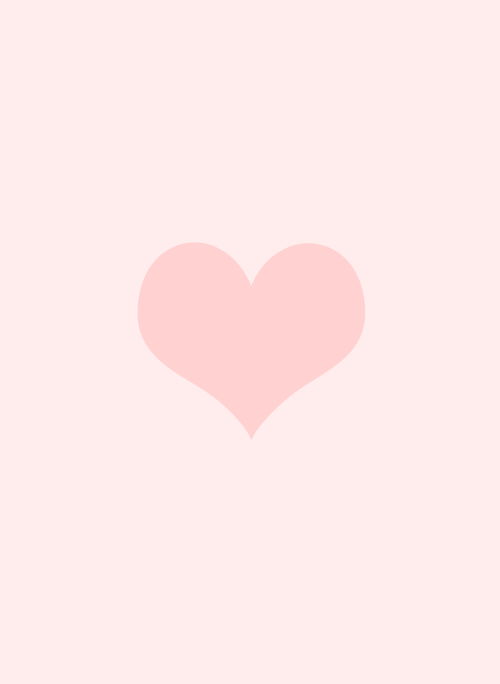蛍の小鼻の左側にはピアスの穴が開いている。
理子がそれに気がついたのは、初めてコンビニの外で会った時だ。
台風の日、うちまで送ってくれた蛍に理子はタオルを貸した。
蛍が、頭の先からスニーカーの先までびしょ濡れだったから。
返さなくても構わないと言ったのに、二日後、蛍は律儀にそれを返しに来た。
自分のものとは明らかに違う柔軟剤の香りがついたそのタオルはなんだか他人のタオルのような、不思議な感じがした。
お礼を言ってドアを閉めようとしたとき、
「俺と付き合ってください。」
突然そう言って頭を下げた蛍を見て、理子は返されたばかりのタオルを落としてしまった。
「…はいぃ?」
「お願いします!」
蛍は頭を下げたまま、バカみたいに大きな
声を出した。
「いやいや、無理ですから。」
「お願いします!」
「いや、無理ですよ。」
「お願いします!」
「だから、無理だって…。」
そこで蛍はようやく顔を上げて、まっすぐに理子を見つめた。
「じゃあ、友達でいいです。最初は。」
譲歩的要請法だ。
最初に無理そうなお願いをして、そのあと少し条件を下げた提案をすると、うけいれてもらいやすいというやつ。
今なら分かるのだけど、その時の理子にはその提案がとても容易いものに見えた。
断り続けるのも体力がいる。
「いいですよ。友達なら。」
それまでずっと固い表情をしていた蛍は心底ほっとしたように笑った。
その顔を見た時に、ああこの子は嘘はついてないな、と理子は思った。
コンビニでよく会うだけのよく知らない、明らかに自分よりも年上の女に交際を申し込む男子高校生なんて、普通に考えればなにか裏があると思うのだろうけど。
蛍の瞳をいくら覗き込んでも、そこにはきれいな群青色の湖しか見えなかった。
「理子、って呼んでも良い?」
少しだけ、照れ臭そうにうつむいた蛍の鼻に光る小さなシルバーのピアスにきづいたのはその時だった。
理子がそれに気がついたのは、初めてコンビニの外で会った時だ。
台風の日、うちまで送ってくれた蛍に理子はタオルを貸した。
蛍が、頭の先からスニーカーの先までびしょ濡れだったから。
返さなくても構わないと言ったのに、二日後、蛍は律儀にそれを返しに来た。
自分のものとは明らかに違う柔軟剤の香りがついたそのタオルはなんだか他人のタオルのような、不思議な感じがした。
お礼を言ってドアを閉めようとしたとき、
「俺と付き合ってください。」
突然そう言って頭を下げた蛍を見て、理子は返されたばかりのタオルを落としてしまった。
「…はいぃ?」
「お願いします!」
蛍は頭を下げたまま、バカみたいに大きな
声を出した。
「いやいや、無理ですから。」
「お願いします!」
「いや、無理ですよ。」
「お願いします!」
「だから、無理だって…。」
そこで蛍はようやく顔を上げて、まっすぐに理子を見つめた。
「じゃあ、友達でいいです。最初は。」
譲歩的要請法だ。
最初に無理そうなお願いをして、そのあと少し条件を下げた提案をすると、うけいれてもらいやすいというやつ。
今なら分かるのだけど、その時の理子にはその提案がとても容易いものに見えた。
断り続けるのも体力がいる。
「いいですよ。友達なら。」
それまでずっと固い表情をしていた蛍は心底ほっとしたように笑った。
その顔を見た時に、ああこの子は嘘はついてないな、と理子は思った。
コンビニでよく会うだけのよく知らない、明らかに自分よりも年上の女に交際を申し込む男子高校生なんて、普通に考えればなにか裏があると思うのだろうけど。
蛍の瞳をいくら覗き込んでも、そこにはきれいな群青色の湖しか見えなかった。
「理子、って呼んでも良い?」
少しだけ、照れ臭そうにうつむいた蛍の鼻に光る小さなシルバーのピアスにきづいたのはその時だった。