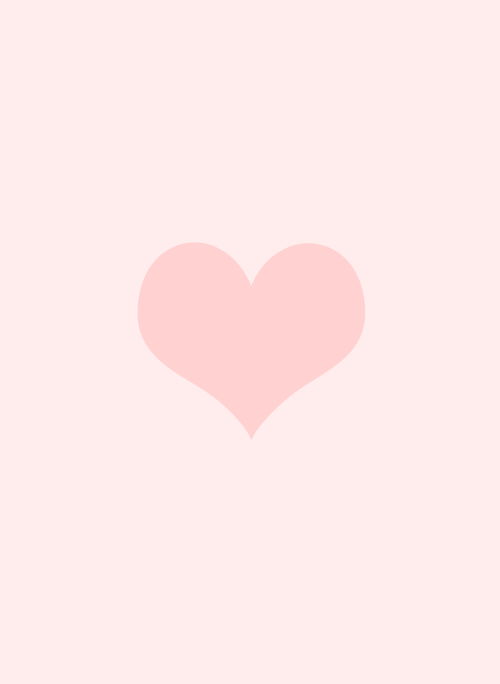「…俺得だけど。」
洋一がそう呟き、そっと明季の背後に腕が回った。ドクンドクンとうるさいのは、自分の心臓なのか洋一の心臓なのかはもうわからない。ただ、その心音に幼い頃のようなおだやかな気持ちを覚える。
目を瞑れば、少しだけ現実を忘れられた。いつの間にか洋一の背に自分も腕を回していた。まるで小さな子供のように。
「…明季。」
「…なに?」
「ちゃんと、震え収まってる。…お前が思ってるより、多分大丈夫だよ。」
そっと後頭部を撫でられると、鼻の奥がつんとした。いつからこんなに脆くて弱い自分になったのだろう。…もしかしたら、もともととても弱い人間だったのかもしれない。その弱さを誰かに見せることは、ずっとしてこなかったはずなのに。
『洋一だからだよ』
なんて言えない。きっとそうだと、わかっているのに。好意をもたれていると知っているから、期待させる言葉を言うのは悪いと思ってしまう。
(…もっとも、抱きしめてなんて期待させまくってるけど。)
矛盾した気持ちばかりが身体中を走りまわって、納得のいくような答えを出してくれない。
ゆっくりと洋一の背に回した腕を解いた。それに合わせて洋一も腕から明季を解放した。頭上から視線を感じるけれど、気まずくて顔を上げることはできない。
「もう、平気か?」
「うん…ごめん、ありがとう。」
「ごめんはいらねーって。」
「だってずるいことしてるって…わかってるし。」
「あー…まぁ、ずるいっちゃずるいか。」
「でしょ?」
「でも、俺がそれでいいっつってんだからいいんだよ。明季は気にすんな。いいからどんどん俺を頼れ。甘えろ。」
「……。」
明季は俯いたままだ。顔なんて上げられない。
「迷惑かけてるかもなんて思わなくていいから、…その代わり、明季にとって大事なときに俺を思い出すことが増えたら、そういうことなんだって自覚して。」
その発言は、洋一の方がずるい。…多分ではなく、絶対に。
洋一がそう呟き、そっと明季の背後に腕が回った。ドクンドクンとうるさいのは、自分の心臓なのか洋一の心臓なのかはもうわからない。ただ、その心音に幼い頃のようなおだやかな気持ちを覚える。
目を瞑れば、少しだけ現実を忘れられた。いつの間にか洋一の背に自分も腕を回していた。まるで小さな子供のように。
「…明季。」
「…なに?」
「ちゃんと、震え収まってる。…お前が思ってるより、多分大丈夫だよ。」
そっと後頭部を撫でられると、鼻の奥がつんとした。いつからこんなに脆くて弱い自分になったのだろう。…もしかしたら、もともととても弱い人間だったのかもしれない。その弱さを誰かに見せることは、ずっとしてこなかったはずなのに。
『洋一だからだよ』
なんて言えない。きっとそうだと、わかっているのに。好意をもたれていると知っているから、期待させる言葉を言うのは悪いと思ってしまう。
(…もっとも、抱きしめてなんて期待させまくってるけど。)
矛盾した気持ちばかりが身体中を走りまわって、納得のいくような答えを出してくれない。
ゆっくりと洋一の背に回した腕を解いた。それに合わせて洋一も腕から明季を解放した。頭上から視線を感じるけれど、気まずくて顔を上げることはできない。
「もう、平気か?」
「うん…ごめん、ありがとう。」
「ごめんはいらねーって。」
「だってずるいことしてるって…わかってるし。」
「あー…まぁ、ずるいっちゃずるいか。」
「でしょ?」
「でも、俺がそれでいいっつってんだからいいんだよ。明季は気にすんな。いいからどんどん俺を頼れ。甘えろ。」
「……。」
明季は俯いたままだ。顔なんて上げられない。
「迷惑かけてるかもなんて思わなくていいから、…その代わり、明季にとって大事なときに俺を思い出すことが増えたら、そういうことなんだって自覚して。」
その発言は、洋一の方がずるい。…多分ではなく、絶対に。