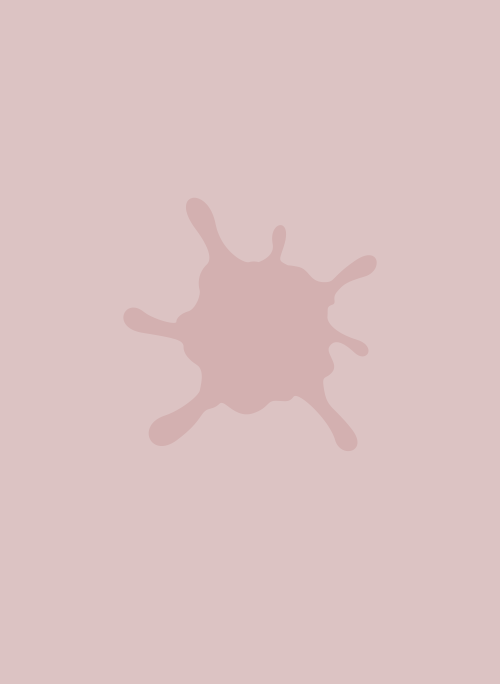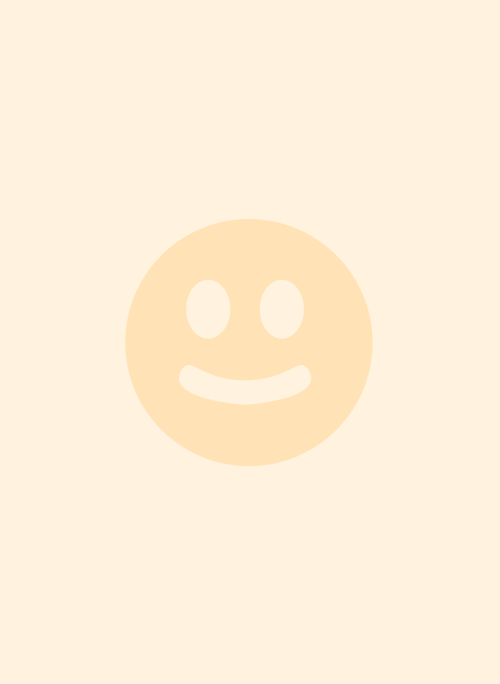『妻の面影』
定年退職をして十年経った日に妻が他界した。
その日、妻は頭が痛いといって、遅くまで布団にもぐっていた。亭主関白だった私は、妻の枕元にいき、「朝飯はつくらないのか?」と無愛想な口調で訊いた。
専業主婦の妻は家事を当たり前にするもの。主人である私は仕事で金を稼ぐもの。
定年退職しても、そう考えていた。のんびり気ままに無職になっても十年もの間、それが今まで仕事に励んできた褒美と思って、妻に協力せず過ごしていたのだ。
「そうですね。頑張ってつくらないと」
そういって起きあがった妻は鮭を焼き、みそ汁をつくり、炊いていた白米を盛り、食卓にすぐに並べてみせた。
いつも通りの朝の食事。奇麗にたいらげた私は「ご馳走さま」とだけ言い、席を離れた。
そして、たいした趣味もつくっていなかった私は二階の自室に入ると、新聞を読んでテレビをつけた。その時、階下で何かが倒れたような音が聞こえたが気にしなかった。
その音が何の音だったのか気づいたのは、お昼はまだだろうかと思って下に降りた午後一時すぎだった。
――既に妻は手遅れの状態だった。
妻が死んだ。葬式の時に、その実感はなかった。それよりも何故、私より先に妻は逝ったのか。介護してもらうはずだったのにという利己主義的な思いがあった。
そして、妻が他界したことで、はじめてひとりの不便さが身に沁みた。
みそ汁にダシを入れることすら知らなかった私だ。掃除も洗濯もはじめて。思った以上に家事が重労働であるということに気づいた。
私は仕事の愚痴を家庭に持ちこんでいたのに、妻は黙って家事をし続けていたのか。そして、私は定年退職した十年もの間、妻に頼り、最期がちかいということすら気がつかなかったのか。
妻が他界して一週間経った日。ようやくそこで後悔の念に駆られて涙を流した。
妻が亡くなってから四十九日が経ち、そろそろ妻の遺品を整理しようかと考え、三面鏡の棚をひく。すると、そこに一冊のメモ帳があった。日記だった。
『晴れ。今日は友達と都心まで買い物に出掛ける。お土産は和菓子でいいかしら。仏壇にも供えられるし、私も練りきりは大好きなので、それにしよう』
『セーターを編むことにした。久しぶりなので本を見ながら。老眼のせいで手が遅くなったみたい。編み終わるまでは内緒にしておこう。定年退職して十年の記念日に渡すといいかしら』
そこまで読んでページを捲る手がとまった。慌てて押し入れを開けて奥を見る。小さな衣装ケースの中から、網棒や本と一緒にセーターが出てきた。そして、手紙も。
『今まで二人一緒に歩いてきて、いろいろと苦労してきましたね。これからはますます手を取りあって進んでいかないとね。私もあなたの体も衰えてきていますから』
愛情とともにこめられた妻からの願い。口には出していなかった感情もあったのかもしれないなと思った。しかし、どう感謝しようとしても妻はもういない。
涙を流しながら遺影の妻に謝るとセーターを着た。妻が最後まで編んでいたセーターは、暖かいだけでなく、心に沁みこむような温かさもあった。
しばらく経って落ち着くと、財布と荷物を手に外に出た。行き先は都心。妻が日記に書いていた場所だ。
今日は妻の大好きだった練りきりを買おう。それを仏壇に供えて、それと家事もはやくマスターしないといけない。そうでないと妻に、まだまだですねと笑われるに違いない。
電車に揺られながら、そんなことを考える。
すると、
「今日はお出かけですか。それは奥さんの手編み?」
ふと、背後から声を掛けられた。振り返ると、よくうちにきていた妻の編み物友達がいた。
雑談をするなかで、必然的に妻の話になる。
「それはセーターベストかしら。けど、あの人ね。袖もつくると言っていたのよ」
「初心者なのですが、私でも続きを編めますかね?」
「袖はパターンも凝らなくていいし簡単よ。よければ、一緒に編み物教室でもどう? 趣味の一環みたいな集まりだから、気軽に習えるわよ」
「そうですね。気分転換に習ってもいいかもしれませんな」
定年退職をして、妻と違う人と言葉を交わしたのは何年振りだろう。
そして、生きていた頃の妻の話が聞けるとは。
目を閉じながら袖なしのセーターに触れる。
すると、セーターを編む網棒の音が聞こえた気がしたのと同時に、妻が「もうすぐで、編み終わりますからね」と言うかのような笑顔がまぶたに浮かんだ。
定年退職をして十年経った日に妻が他界した。
その日、妻は頭が痛いといって、遅くまで布団にもぐっていた。亭主関白だった私は、妻の枕元にいき、「朝飯はつくらないのか?」と無愛想な口調で訊いた。
専業主婦の妻は家事を当たり前にするもの。主人である私は仕事で金を稼ぐもの。
定年退職しても、そう考えていた。のんびり気ままに無職になっても十年もの間、それが今まで仕事に励んできた褒美と思って、妻に協力せず過ごしていたのだ。
「そうですね。頑張ってつくらないと」
そういって起きあがった妻は鮭を焼き、みそ汁をつくり、炊いていた白米を盛り、食卓にすぐに並べてみせた。
いつも通りの朝の食事。奇麗にたいらげた私は「ご馳走さま」とだけ言い、席を離れた。
そして、たいした趣味もつくっていなかった私は二階の自室に入ると、新聞を読んでテレビをつけた。その時、階下で何かが倒れたような音が聞こえたが気にしなかった。
その音が何の音だったのか気づいたのは、お昼はまだだろうかと思って下に降りた午後一時すぎだった。
――既に妻は手遅れの状態だった。
妻が死んだ。葬式の時に、その実感はなかった。それよりも何故、私より先に妻は逝ったのか。介護してもらうはずだったのにという利己主義的な思いがあった。
そして、妻が他界したことで、はじめてひとりの不便さが身に沁みた。
みそ汁にダシを入れることすら知らなかった私だ。掃除も洗濯もはじめて。思った以上に家事が重労働であるということに気づいた。
私は仕事の愚痴を家庭に持ちこんでいたのに、妻は黙って家事をし続けていたのか。そして、私は定年退職した十年もの間、妻に頼り、最期がちかいということすら気がつかなかったのか。
妻が他界して一週間経った日。ようやくそこで後悔の念に駆られて涙を流した。
妻が亡くなってから四十九日が経ち、そろそろ妻の遺品を整理しようかと考え、三面鏡の棚をひく。すると、そこに一冊のメモ帳があった。日記だった。
『晴れ。今日は友達と都心まで買い物に出掛ける。お土産は和菓子でいいかしら。仏壇にも供えられるし、私も練りきりは大好きなので、それにしよう』
『セーターを編むことにした。久しぶりなので本を見ながら。老眼のせいで手が遅くなったみたい。編み終わるまでは内緒にしておこう。定年退職して十年の記念日に渡すといいかしら』
そこまで読んでページを捲る手がとまった。慌てて押し入れを開けて奥を見る。小さな衣装ケースの中から、網棒や本と一緒にセーターが出てきた。そして、手紙も。
『今まで二人一緒に歩いてきて、いろいろと苦労してきましたね。これからはますます手を取りあって進んでいかないとね。私もあなたの体も衰えてきていますから』
愛情とともにこめられた妻からの願い。口には出していなかった感情もあったのかもしれないなと思った。しかし、どう感謝しようとしても妻はもういない。
涙を流しながら遺影の妻に謝るとセーターを着た。妻が最後まで編んでいたセーターは、暖かいだけでなく、心に沁みこむような温かさもあった。
しばらく経って落ち着くと、財布と荷物を手に外に出た。行き先は都心。妻が日記に書いていた場所だ。
今日は妻の大好きだった練りきりを買おう。それを仏壇に供えて、それと家事もはやくマスターしないといけない。そうでないと妻に、まだまだですねと笑われるに違いない。
電車に揺られながら、そんなことを考える。
すると、
「今日はお出かけですか。それは奥さんの手編み?」
ふと、背後から声を掛けられた。振り返ると、よくうちにきていた妻の編み物友達がいた。
雑談をするなかで、必然的に妻の話になる。
「それはセーターベストかしら。けど、あの人ね。袖もつくると言っていたのよ」
「初心者なのですが、私でも続きを編めますかね?」
「袖はパターンも凝らなくていいし簡単よ。よければ、一緒に編み物教室でもどう? 趣味の一環みたいな集まりだから、気軽に習えるわよ」
「そうですね。気分転換に習ってもいいかもしれませんな」
定年退職をして、妻と違う人と言葉を交わしたのは何年振りだろう。
そして、生きていた頃の妻の話が聞けるとは。
目を閉じながら袖なしのセーターに触れる。
すると、セーターを編む網棒の音が聞こえた気がしたのと同時に、妻が「もうすぐで、編み終わりますからね」と言うかのような笑顔がまぶたに浮かんだ。