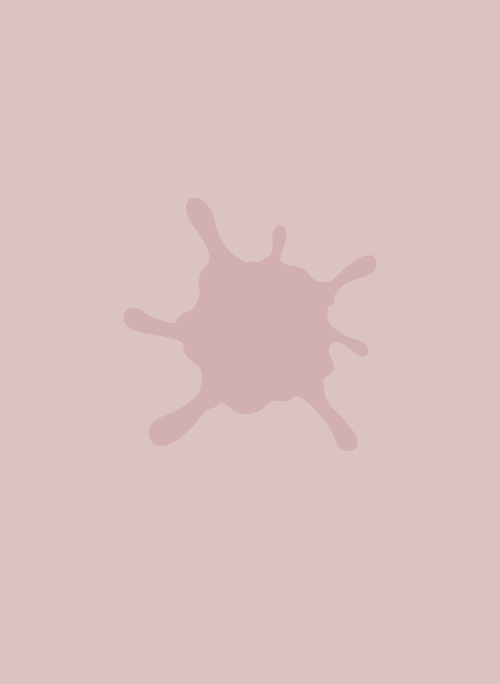「そう…」
深く聞いてこないことに少し安心した。
目を見られれば忌み子だと気付かれてしまうかもしれないという恐怖から男の顔は見れないが、男が少し考え込んでいる様子は伺えた。
「あの、大丈夫です。ご親切にありがとうございます。」
こんな優しい人の気分は害したくなかった。精一杯の敬意を込めて頭を下げ、早々に立ち去ろうとすると男は少女の手を優しく握り微笑んだ。
「じゃあ、僕についてくる?」
「…え?」
「僕の家はけっこう広いんだ。君1人くらい面倒見られるよ。家族が多いから君が良ければ、だけど…」
私は驚いてしまい、思わず男の目を凝視してしまった。