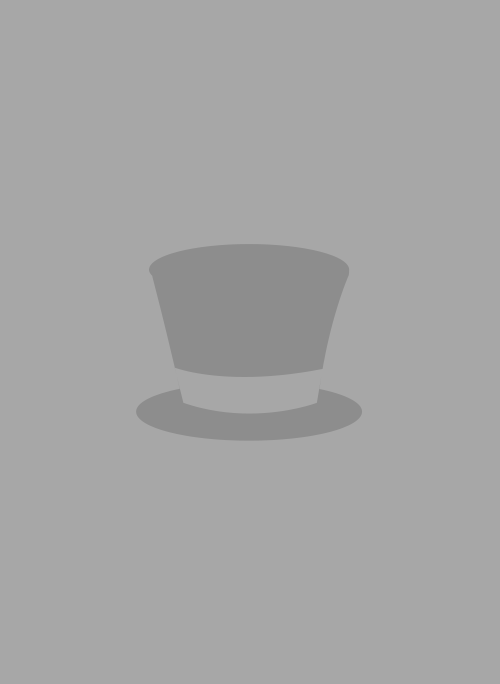里沙は、大して可愛くもないし美人でもないし、成績が優秀ってわけでもない。
あんまり取り柄がないように見える上、あの特徴ある間延び口調だ。
…本当は、里沙がいじめられても、可笑しくない。
里沙は、そんな危ない立ち位置なのだ。
それがこのクラスで上位の位置にいられるのは。
里沙本人も言っていたけど、私がいるから。
私は里沙に同情して、一緒にいるのではない。
私は友達として、里沙のことが好きなのだ。
卒業しても大人になっても、別れたくないと思う、大事な親友。
里沙が私をどう思っているのかは知らないけど。
私は見返りを求めず、無条件に里沙を信頼していた。
里沙が危険な橋を渡るのなら。
私も一緒に渡って良いと思っている。
例えそれが、今にも落ちてしまいそうな橋でも。
里沙も、少しはそう思っているはずだ。
―――だから、“こんなこと”が出来るのだ。
“こんなこと”が出来るのは、私が危ない橋を渡っていて、それに里沙も一緒に渡っているから。
最後まで渡るのか、途中で折り返すのか、それはわからないけど。
「……フフフッ」
今まで黙って“作業”をしていた里沙が、笑みを漏らした。
それにつられるように、私も一緒に笑った。