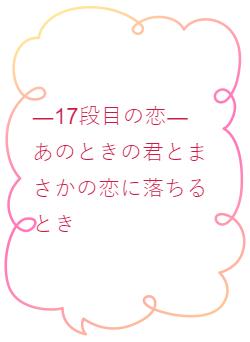台風が接近し、窓ガラスに打ち付けられる雨音を聞きながら、
鳥たちとセミの大合唱に覆われながら、
どこかの部屋から聞こえるチリンという風鈴の音を聞きながら、
そんなふうに夏を耳管で感じながら、勉強会は5回目を終えていた。
汗を浮かべた美弥の肌を、長い指でつかんだ氷で優がなでていく。
氷は肌を滑るたびに溶け、美弥の体を濡らす。最後に小さく小さくなった氷の塊を体の上に置き去りにして、優は美弥の脇と胸の間に顔をうずめた。
そしてそんな親密な恰好で、「盆休みは何するの?」と、ありきたりなことを聞く。
脇に息がかかってくすぐったいのに。
「特に決めてないけど、夏っぽいことしたい。緑に囲まれて昼からビール飲んだり、花火したり。泳ぎにも行きたい。でもどこも混んでるからなあ」
「俺、すごくいい場所知ってる。自然に囲まれていて、静かなプールもあって、テラスで冷たいビールも飲める」
「どこそれ?」
「行きたい?」
「行きたい」
「じゃあ連れてってやる。だから――」
優は美弥の体からすり抜け顔を起こして、もう一度美弥の体を抱いた。
鳥たちとセミの大合唱に覆われながら、
どこかの部屋から聞こえるチリンという風鈴の音を聞きながら、
そんなふうに夏を耳管で感じながら、勉強会は5回目を終えていた。
汗を浮かべた美弥の肌を、長い指でつかんだ氷で優がなでていく。
氷は肌を滑るたびに溶け、美弥の体を濡らす。最後に小さく小さくなった氷の塊を体の上に置き去りにして、優は美弥の脇と胸の間に顔をうずめた。
そしてそんな親密な恰好で、「盆休みは何するの?」と、ありきたりなことを聞く。
脇に息がかかってくすぐったいのに。
「特に決めてないけど、夏っぽいことしたい。緑に囲まれて昼からビール飲んだり、花火したり。泳ぎにも行きたい。でもどこも混んでるからなあ」
「俺、すごくいい場所知ってる。自然に囲まれていて、静かなプールもあって、テラスで冷たいビールも飲める」
「どこそれ?」
「行きたい?」
「行きたい」
「じゃあ連れてってやる。だから――」
優は美弥の体からすり抜け顔を起こして、もう一度美弥の体を抱いた。