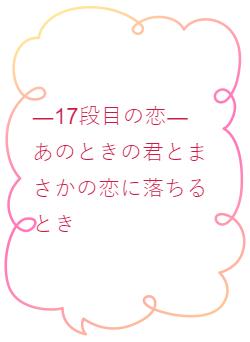「僕はときどき感じるんだ。あ、美弥さんは今、優君のこと考えてる、って」
トン、と心の奥を、生美の細い指で強く突かれた気がした。
「そんなことないわ」と言ってはみたが、正直に言えば確かに美弥は未だにふと優を思い出すことがあった。
でもそれは、未練ではなく、ただ思い出すだけなのだと言い訳したかったが、生美にしてみればそれは同じことなのだ。
美弥は言葉にできず、目を伏せた。
「美弥さんの心の底には、まだ優くんへの小さな火がくすぶっているんじゃないか、それがいつか燃え出すんじゃないかって不安に駆られるときがある。情けないけど、僕はそんな風に怯えているんだ。だから優君と会って、彼の言い訳をちゃんと聞いて、自分の気持ちを確かめて欲しい。そして決めてほしい。残り火を消すのか、燃やすのか――」
トン、と心の奥を、生美の細い指で強く突かれた気がした。
「そんなことないわ」と言ってはみたが、正直に言えば確かに美弥は未だにふと優を思い出すことがあった。
でもそれは、未練ではなく、ただ思い出すだけなのだと言い訳したかったが、生美にしてみればそれは同じことなのだ。
美弥は言葉にできず、目を伏せた。
「美弥さんの心の底には、まだ優くんへの小さな火がくすぶっているんじゃないか、それがいつか燃え出すんじゃないかって不安に駆られるときがある。情けないけど、僕はそんな風に怯えているんだ。だから優君と会って、彼の言い訳をちゃんと聞いて、自分の気持ちを確かめて欲しい。そして決めてほしい。残り火を消すのか、燃やすのか――」