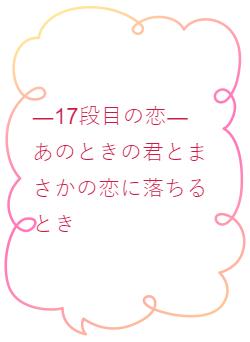「やだっ、たこ焼きもおいしそ~う」
彦摩呂が目を見開く。
「たこ焼きじゃなくて、焼いている男がおいしそうなんでしょ」
「あらあ、なんでわかるのぉ~?」
からみつくような太い声を出し、目をぱちぱちさせる。
「だってあの男子、もろ彦摩呂先生の好みだし、それに先生、たこ焼き嫌いじゃないですか」
「もぉ、生美は私のこと、何でも知ってるのよね」
彦摩呂の甘えたそぶりに「ええ、一応、先生の恋人だと思われてますから」と、生美はそっけなく返す。
「それにしても今日はいつにもまして先生の衣装、いや洋服、派手じゃないですか?」
彦摩呂が羽織っている春用のロングコートの生地は西陣織、中にきているニットは桜もめまいを起こすほどのビビッドなピンクで、パンツは光沢のあるシルバーだ。
「人気者のあんたが目立たないようわざとハデにしてきてあげたのよ」
「先生がそんなに目立ったら、結局一緒にいる僕らもみんな目立っちゃうじゃないですか」
彦摩呂が聞こえない振りをして屋台に目をそらすのは、たぶん同意しているからだろう。
彦摩呂が目を見開く。
「たこ焼きじゃなくて、焼いている男がおいしそうなんでしょ」
「あらあ、なんでわかるのぉ~?」
からみつくような太い声を出し、目をぱちぱちさせる。
「だってあの男子、もろ彦摩呂先生の好みだし、それに先生、たこ焼き嫌いじゃないですか」
「もぉ、生美は私のこと、何でも知ってるのよね」
彦摩呂の甘えたそぶりに「ええ、一応、先生の恋人だと思われてますから」と、生美はそっけなく返す。
「それにしても今日はいつにもまして先生の衣装、いや洋服、派手じゃないですか?」
彦摩呂が羽織っている春用のロングコートの生地は西陣織、中にきているニットは桜もめまいを起こすほどのビビッドなピンクで、パンツは光沢のあるシルバーだ。
「人気者のあんたが目立たないようわざとハデにしてきてあげたのよ」
「先生がそんなに目立ったら、結局一緒にいる僕らもみんな目立っちゃうじゃないですか」
彦摩呂が聞こえない振りをして屋台に目をそらすのは、たぶん同意しているからだろう。