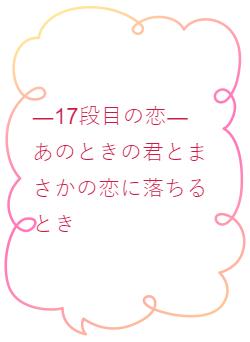3月も半ばになって、ようやく2人で会える時間が増えていった。
帰りはいつも生美に送られ、別れる間際に自然と唇を重ねるまでの関係になった。
沈丁花の香りが増すなかで、生美の唇が溶けてゆく。
それでも「部屋に行っていい?」とは生美は効かないし、美弥も自分の部屋に、優と過ごした部屋に生美を誘うことには躊躇を感じた。
「おやすみ」
頬を包み、美弥の顔を覗き込む生美の瞳はいつも美弥を求めていたし、いつも明るい生美の声は、別れの間際にだけは湿り気を増す。
それでも生美は、美弥の心が決して波立たないよう、辛抱強く待っていてくれる。
「愛おしい」と思う。
愛おしい、愛おしい、愛おしい。
美弥は愛おしさを吐息に乗せて「おやすみなさい」と返す。
帰りはいつも生美に送られ、別れる間際に自然と唇を重ねるまでの関係になった。
沈丁花の香りが増すなかで、生美の唇が溶けてゆく。
それでも「部屋に行っていい?」とは生美は効かないし、美弥も自分の部屋に、優と過ごした部屋に生美を誘うことには躊躇を感じた。
「おやすみ」
頬を包み、美弥の顔を覗き込む生美の瞳はいつも美弥を求めていたし、いつも明るい生美の声は、別れの間際にだけは湿り気を増す。
それでも生美は、美弥の心が決して波立たないよう、辛抱強く待っていてくれる。
「愛おしい」と思う。
愛おしい、愛おしい、愛おしい。
美弥は愛おしさを吐息に乗せて「おやすみなさい」と返す。