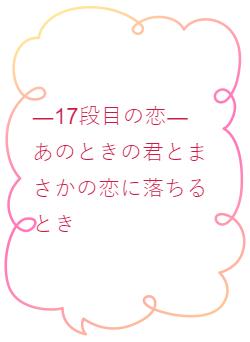「わかった。私、少しずつ生美くんの虜になるわ」
泣きそうな気持ちを押さえて冗談ぽく言うと、「できればピッチを上げてね」と生美の顔がほころんだ。
食事の後にバーに立ち寄った。
カウンターだけのシックな店内には会話を邪魔しない程度のジャズが流れ、外のにぎわいとは別世界の静かな時間が流れていた。
美弥はきれいな橙色のミモザを、生美はサイドカーを注文し、飲み始めてすぐに「あっ、忘れてた」と言って、生美がジャケットの内ポケットから小さな箱を取り出した。
それを見て「あ、私も」と、美弥もバッグから包みを取り出し生美の前に差し出した。
お互いに包みを開ける。
美弥からはアイルランドのブランドのソフトドニゴールの手織りのマフラー。
優しさのあるネイビーの色合いが生美にピッタリだと思ったのだ。
泣きそうな気持ちを押さえて冗談ぽく言うと、「できればピッチを上げてね」と生美の顔がほころんだ。
食事の後にバーに立ち寄った。
カウンターだけのシックな店内には会話を邪魔しない程度のジャズが流れ、外のにぎわいとは別世界の静かな時間が流れていた。
美弥はきれいな橙色のミモザを、生美はサイドカーを注文し、飲み始めてすぐに「あっ、忘れてた」と言って、生美がジャケットの内ポケットから小さな箱を取り出した。
それを見て「あ、私も」と、美弥もバッグから包みを取り出し生美の前に差し出した。
お互いに包みを開ける。
美弥からはアイルランドのブランドのソフトドニゴールの手織りのマフラー。
優しさのあるネイビーの色合いが生美にピッタリだと思ったのだ。