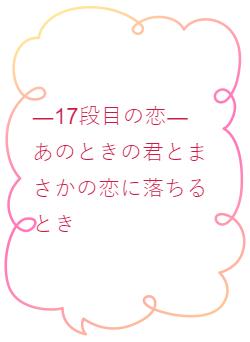美弥は生美をちろっと睨んで、「それ褒めてないよね」と生美の頭に帽子を返した。
「褒めてるよ。こんな帽子が似合うって、相当いい女ってことだもん」
今度はしっかり睨んで言う。
「年上をからかわないこと」
「からかってないよ。ところでサンタからお願い」
「なあに?」
生美が美弥の耳元に口を寄せ、まるで誰にも聞かれてはいけないとても大事なことを伝えるように、そっと耳打ちした。
「手をつなごう」
この数カ月間、生美と美弥は急接近して一緒に過ごす時間を重ねてきたが、まだ手をつないだこともない。
2人の間にはぎりぎり友達のラインが引かれたままになっていて、別にそれは無理していたわけでも不自然でもなく、その状態が穏やかに心地よく続いていた。
別に手をつないだからといって、どうってことはない。
そこに大した意味が生まれるわけでもない。
それなのに「お願い」なんて言われると、そこに特別な甘い響きが乗った気がして、美弥の胸はとくんとした。
「褒めてるよ。こんな帽子が似合うって、相当いい女ってことだもん」
今度はしっかり睨んで言う。
「年上をからかわないこと」
「からかってないよ。ところでサンタからお願い」
「なあに?」
生美が美弥の耳元に口を寄せ、まるで誰にも聞かれてはいけないとても大事なことを伝えるように、そっと耳打ちした。
「手をつなごう」
この数カ月間、生美と美弥は急接近して一緒に過ごす時間を重ねてきたが、まだ手をつないだこともない。
2人の間にはぎりぎり友達のラインが引かれたままになっていて、別にそれは無理していたわけでも不自然でもなく、その状態が穏やかに心地よく続いていた。
別に手をつないだからといって、どうってことはない。
そこに大した意味が生まれるわけでもない。
それなのに「お願い」なんて言われると、そこに特別な甘い響きが乗った気がして、美弥の胸はとくんとした。