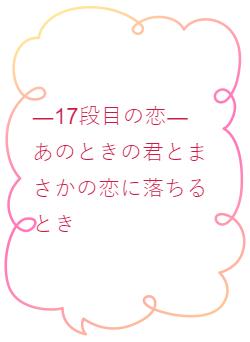ウエイターが、ビールを運んできた。
いかにも冷えてます、というように、グラスには小さな、小さな水滴が張り付いていた。
優は先にグラスを持ち上げ、「お疲れ」と言って喉に流し込んだ。
そのとき、優の肩で、窓から差し込む明りに反射して、何かがきらっと光った。
綾香がその光るものに手を伸ばし、「これ」と指につまんで目の前に持ち上げた。
1本の艶やかな髪の毛だった。
「これ、優君のじゃないね」
白い指に挟まれた髪は、浅い茶色で、短くはなかったが、ロングヘアと言えるほどに長くもなかった。
優も綾香も長い髪でなかったことにホッとしたのは同じだが、綾香はそれでも自分のものではない髪の毛を見つめ、誰のものだろうと考える。
いかにも冷えてます、というように、グラスには小さな、小さな水滴が張り付いていた。
優は先にグラスを持ち上げ、「お疲れ」と言って喉に流し込んだ。
そのとき、優の肩で、窓から差し込む明りに反射して、何かがきらっと光った。
綾香がその光るものに手を伸ばし、「これ」と指につまんで目の前に持ち上げた。
1本の艶やかな髪の毛だった。
「これ、優君のじゃないね」
白い指に挟まれた髪は、浅い茶色で、短くはなかったが、ロングヘアと言えるほどに長くもなかった。
優も綾香も長い髪でなかったことにホッとしたのは同じだが、綾香はそれでも自分のものではない髪の毛を見つめ、誰のものだろうと考える。