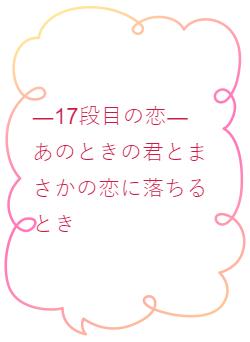東京に戻る車の中で、美弥と生美はすっかり打ち解けていた。
学生時代に同じ環境で過ごしたという体験は、懐かしさと親近感を抱かせる。同じ校舎の中で、同じルールに従って、同じ風景を見て育った7年間を思い出すだけで、これまで口をきいたことがなかったにもかかわらず、2人は昔からの友達のような錯覚を覚えるのだ。
「美弥さん、今度ご飯行きましょうよ。僕、美味しいところいっぱい知ってるから」
後部シートの美弥に体ごと向き直り、生美がはい、これ、と自分の名刺を渡した。
「その番号からかかってきたら僕だから、ちゃんと出てね……て、美弥さんの番号知らなかった」
淡いアイボリーの和紙を使った名刺には、『ーアーティスト・沖田生美』という肩書のほかに、彼の事務所のアドレスと電話番号、メールアドレス、携帯電話番号が書かれていた。
へえ。アーティストも名刺を持ち歩くのか、と、美弥は名刺に書かれた番号にその場でかけてみた。
学生時代に同じ環境で過ごしたという体験は、懐かしさと親近感を抱かせる。同じ校舎の中で、同じルールに従って、同じ風景を見て育った7年間を思い出すだけで、これまで口をきいたことがなかったにもかかわらず、2人は昔からの友達のような錯覚を覚えるのだ。
「美弥さん、今度ご飯行きましょうよ。僕、美味しいところいっぱい知ってるから」
後部シートの美弥に体ごと向き直り、生美がはい、これ、と自分の名刺を渡した。
「その番号からかかってきたら僕だから、ちゃんと出てね……て、美弥さんの番号知らなかった」
淡いアイボリーの和紙を使った名刺には、『ーアーティスト・沖田生美』という肩書のほかに、彼の事務所のアドレスと電話番号、メールアドレス、携帯電話番号が書かれていた。
へえ。アーティストも名刺を持ち歩くのか、と、美弥は名刺に書かれた番号にその場でかけてみた。