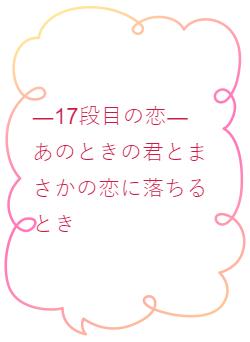その後ろを、優も浮き輪を抱えて追いかけた。
伊豆は東京からそう遠くはないのに、海水の透明度は抜群で、水底の白い砂が透けている。
美弥は海の中を歩いて進み、腰まで水に浸かったところで沖に向かって泳ぎ始めた。
そして背が立たない深さの場所まで行くと、そこでくるりと仰向けになって体を浮かせた。
真っ青な空が広がっている。
海の水の冷たさが、太陽から降り注ぐ熱を中和してくれる。
目をつぶり、全身の力を抜いて水に体をゆだねた。
ゆらゆらゆらゆら、波と一緒に揺られていえると、何とも言えない心地よさに包まれる。
なにもない、ただ夏の真ん中に漂っている気分。
優は浮き輪に上半身を乗せて波に浮きながら、そんな美弥を少し離れた場所で見ていた。
水着から伸びるすらりとした手足を伸ばし、たまに波に傾きながらも目を開けることはなく、まるで眠っているかのようだ。
伊豆は東京からそう遠くはないのに、海水の透明度は抜群で、水底の白い砂が透けている。
美弥は海の中を歩いて進み、腰まで水に浸かったところで沖に向かって泳ぎ始めた。
そして背が立たない深さの場所まで行くと、そこでくるりと仰向けになって体を浮かせた。
真っ青な空が広がっている。
海の水の冷たさが、太陽から降り注ぐ熱を中和してくれる。
目をつぶり、全身の力を抜いて水に体をゆだねた。
ゆらゆらゆらゆら、波と一緒に揺られていえると、何とも言えない心地よさに包まれる。
なにもない、ただ夏の真ん中に漂っている気分。
優は浮き輪に上半身を乗せて波に浮きながら、そんな美弥を少し離れた場所で見ていた。
水着から伸びるすらりとした手足を伸ばし、たまに波に傾きながらも目を開けることはなく、まるで眠っているかのようだ。