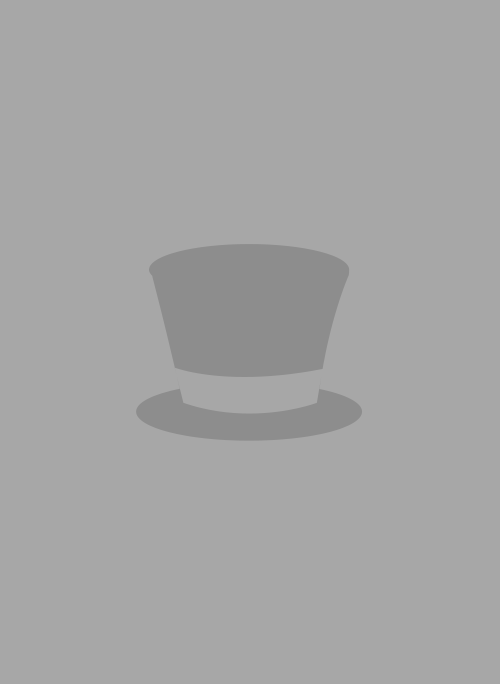初めて舞に会った日から一週間が過ぎた。
この一週間、透はよく舞の事を思い出していた。
無邪気に笑う顔、泣いた顔、拗ねた顔、恥ずかしそうにした顔…どの表情も透にとっては眩しく思えた。
学生時代、言い寄って来た女性は自慢ではないが人並み以上に居た。
けれど透は弁護士になる事だけ思い続けていたせいか、少しも気にならなかった。
しかも両親を見て育ったせいか愛し合うという表現を理解していない。
だから自分を好きだと言われても、その言葉の意味も相手の気持ちも理解出来ないでいた。
そんな透の頭の中を舞が埋めようとしていた。
正直透自身この一週間は自分が自分でないような気でならない。
何をするにも、何処かうわの空だったりして失敗が目立っていた。
「おいっ!深海…お前最近変やぞ??」
五十嵐のテーブルにお茶を持って来たのだけど、置き損ない湯呑みを倒してしまった。
慌てて拭く透に五十嵐は困り果てた顔で心配そうに言った。
「すみません。自分でもなんでだかわからなくて…。」
「…今日は取り敢えず仕事はひと段落したし…よし、俺が話を聞いたる。もちろん初回やから無料や!」
そう言って豪快に笑った。
透は自分の椅子を五十嵐の横につけた。
「僕なんかの病気かもしれないです。」
「なんやて?それホンマか?どこか痛いとこでもあるんか?」
「いえ…痛いってわけじゃないんです。その…五十嵐さんの姪御さんの…」
「舞か?なんや、あいつなんかしでかしたか?」
「いや、そうじゃなくて…毎日気になるんです。舞さんの事考えてしまうんです。」
「はぁ?なんやそれ!?」
五十嵐は先程よりも豪快さを増して笑った。
「ちょっ…五十嵐さん?なんで笑うんですか??」
透は恥ずかしさと怒りを露わにした。
「深海それ本気の悩みか?」
五十嵐はお腹を抑えて笑うのを我慢しながら透に聞いた。
「本気ですよ…じゃないとわざわざ相談なんてしません。」
「そやな、悪かった。お前の悩み笑ったりして…。」
五十嵐は子供をあやす様に透の頭を撫でた。
「子供扱いしないでください。」
「悪かったって。そない怒んなよ…深海、それ病気でもなんでもない。ただの恋や。」
「こ…い……って恋!?僕がですか?相手は女子高生ですよ?そんなこと…。」
「アカンこりゃ病気やわ。恋の病やな。そないなこと自分でもわからんなんて、今時そんな奴いるんやな。それに舞は女子高生やけど、お前と10しか変わらん。もっと年重ねれば、そんな気にならん事やと思うで。」
透は五十嵐の言葉が理解出来ずにいた。
「お〜い。聞いとるか?深海?深海くん?…透ちゃ〜ん?」
五十嵐は透の目の前で手をパタパタとひらつかせた。
「僕が…あの子に…。」
「そや、誰かを好きになるなんてもんは、ここやなくてココで決めることや。」
そう言って五十嵐は透の頭を指し、その後胸を指した。
「ココで決めること…。五十嵐さん…僕どうしたらいいんでしょう?誰かを…その好きなるってこと初めてなんです。」
五十嵐は初めて透と会った事を思い出した。
一見優しそうな青年だけど、時折心がないような表現を見せると思った。
その青年が今恋する事を知って目が変わった様に思えた。
「そやな…俺が知る限りでは舞に男はおらん。」
その言葉を聞いて透はホッとした。
五十嵐に恋をしてると言われてから透の気持ちは一喜一憂しだした。
「あの…五十嵐さんはいいんですか…その舞さんと…。」
「付き合うことになってもってことか?」
言葉に詰まらせた透の代わりに五十嵐が透の聞きたい事を口にした。
「はい…。」
「俺に聞かれてもなぁ…。」
五十嵐は困ったように頭を掻いた。
「そうだな、俺はいいと思う。だって、俺はお前が好きやぞ。素直でいい奴やと思う。」
不意に五十嵐に褒められ透は素直に嬉しく思った。
こんな風に面と向かって【好き】だと言ってくれた大人はいなかったからだ。
家の中では親は居なく、たまに帰って来たと思えば何かを言うわけでもなく顔を合わせてしまったら溜息ばかり聞かされていた。
ずっと自分自身はこの世で生きていてはいけない物だと思っていた。
だから、あの日アイツを殺して自分も殺すつもりだった。
けれど透は生きる道を選んで今、不謹慎にも生きてきてよかったと思えた。
「だからきっと、舞もお前を気にいるさ。」
そう言ってまた透の頭を撫でた。
今度は素直に五十嵐の手の温もりを受け入れた。
透は考えた。
このモヤモヤした物が恋というのだと知った今自分は何をすればいいのか?
今度何処かに誘う?
いや、それは急過ぎる。
じゃ食事に誘う?
高校生の女の子が好む物がわからない。
けれど、そもそも自分が誰かを好きになって幸せを望む事が許されるのだろうか?
「僕が恋なんてしていいのかな?」
心の想いが口に出た。
「良いに決まってやろ。恋することは生きていれば誰にでも起こる感情なんや。もちろん俺にだってな!だからお前の気持ちは当たり前や。なんせ、俺の姪やからな!」
五十嵐はニカっと笑った。
透は勝手にも五十嵐に言われた言葉が、あの人に言われてる様な気がした。
『いいよ。』って言われた気がした。
「ありがとうございます。僕頑張ってみます。」
「おぉまたなんかあったら、なんでも相談してき。」
五十嵐はそう言ってコーヒーを淹れ透の前に差し出した。
「はい…さっそくなんですが舞さんは何が好きなんですか?食べ物とか、趣味とか…。」
五十嵐はう〜んと首を捻り考えた。
「そや、焼肉は好きやな!この前の焼肉もアイツのリクエストやったからな。あと寿司も好きみたいやぞ。たまに連れてけって催促されるからなぁ。趣味かぁ…趣味なぁ…なんやろな……。友達とはよくカラオケとか映画行ってるみたいやな。たまに見せられるプリクラってやつに、なんかそないな事書いてあった様な気がするわ。」
「映画ですか!?僕も好きです、映画!」
興奮した透の声はうわずった。
透は遊ぶ友達なんてものは一人も居なかった。
殆どの時間、家で過ごしていた透にとってテレビが友達みたいな物だった。
そんな透にとって映画という世界は自分を色んな世界へと連れて行ってくれる魔法みたいな物だった。
毎日何かしら一本は映画を観ていた。
多い時で一日8本観る時もあった。
ジャンル関係なく、どんな作品も観てきた。
ただ弁護士を目指すようになってからは、その時間の全てを勉強に費やしてきたので、ここ数年まともに映画を観ていない。
そろそろ落ち着いてきたから、観に行こうかと思っていたところだった。
「映画誘ってみてもいいでしょうか?」
興奮したまま透は五十嵐に問う。
「俺に聞かれてもなぁ…いっぺん誘ってみたらええんとちゃうか?!もしアイツとお前の休みが合わんねんやったら、都合つけたるから。」
五十嵐の優しさが透を一層興奮させた。
透は五十嵐の手を取りブンブンと上下に揺らした。
「ありがとうございます!!」
「わかったわかった。落ち着け!誘ってみてからの話やろ?!」
「あっはい、電話してみます。」
そう言って透はズボンのポケットから携帯を取り出した。
「おいっ今は仕事中やぞ!」
五十嵐は意地悪で透に告げた。
間に受けた透は慌てて携帯を仕舞う。
それを見た五十嵐は笑った。
五十嵐は透に嘘だと言ったけれど、真面目な透に冗談は冗談にならず、「仕事が終わってからにします。」と、言って仕事を再開した。
この一週間、透はよく舞の事を思い出していた。
無邪気に笑う顔、泣いた顔、拗ねた顔、恥ずかしそうにした顔…どの表情も透にとっては眩しく思えた。
学生時代、言い寄って来た女性は自慢ではないが人並み以上に居た。
けれど透は弁護士になる事だけ思い続けていたせいか、少しも気にならなかった。
しかも両親を見て育ったせいか愛し合うという表現を理解していない。
だから自分を好きだと言われても、その言葉の意味も相手の気持ちも理解出来ないでいた。
そんな透の頭の中を舞が埋めようとしていた。
正直透自身この一週間は自分が自分でないような気でならない。
何をするにも、何処かうわの空だったりして失敗が目立っていた。
「おいっ!深海…お前最近変やぞ??」
五十嵐のテーブルにお茶を持って来たのだけど、置き損ない湯呑みを倒してしまった。
慌てて拭く透に五十嵐は困り果てた顔で心配そうに言った。
「すみません。自分でもなんでだかわからなくて…。」
「…今日は取り敢えず仕事はひと段落したし…よし、俺が話を聞いたる。もちろん初回やから無料や!」
そう言って豪快に笑った。
透は自分の椅子を五十嵐の横につけた。
「僕なんかの病気かもしれないです。」
「なんやて?それホンマか?どこか痛いとこでもあるんか?」
「いえ…痛いってわけじゃないんです。その…五十嵐さんの姪御さんの…」
「舞か?なんや、あいつなんかしでかしたか?」
「いや、そうじゃなくて…毎日気になるんです。舞さんの事考えてしまうんです。」
「はぁ?なんやそれ!?」
五十嵐は先程よりも豪快さを増して笑った。
「ちょっ…五十嵐さん?なんで笑うんですか??」
透は恥ずかしさと怒りを露わにした。
「深海それ本気の悩みか?」
五十嵐はお腹を抑えて笑うのを我慢しながら透に聞いた。
「本気ですよ…じゃないとわざわざ相談なんてしません。」
「そやな、悪かった。お前の悩み笑ったりして…。」
五十嵐は子供をあやす様に透の頭を撫でた。
「子供扱いしないでください。」
「悪かったって。そない怒んなよ…深海、それ病気でもなんでもない。ただの恋や。」
「こ…い……って恋!?僕がですか?相手は女子高生ですよ?そんなこと…。」
「アカンこりゃ病気やわ。恋の病やな。そないなこと自分でもわからんなんて、今時そんな奴いるんやな。それに舞は女子高生やけど、お前と10しか変わらん。もっと年重ねれば、そんな気にならん事やと思うで。」
透は五十嵐の言葉が理解出来ずにいた。
「お〜い。聞いとるか?深海?深海くん?…透ちゃ〜ん?」
五十嵐は透の目の前で手をパタパタとひらつかせた。
「僕が…あの子に…。」
「そや、誰かを好きになるなんてもんは、ここやなくてココで決めることや。」
そう言って五十嵐は透の頭を指し、その後胸を指した。
「ココで決めること…。五十嵐さん…僕どうしたらいいんでしょう?誰かを…その好きなるってこと初めてなんです。」
五十嵐は初めて透と会った事を思い出した。
一見優しそうな青年だけど、時折心がないような表現を見せると思った。
その青年が今恋する事を知って目が変わった様に思えた。
「そやな…俺が知る限りでは舞に男はおらん。」
その言葉を聞いて透はホッとした。
五十嵐に恋をしてると言われてから透の気持ちは一喜一憂しだした。
「あの…五十嵐さんはいいんですか…その舞さんと…。」
「付き合うことになってもってことか?」
言葉に詰まらせた透の代わりに五十嵐が透の聞きたい事を口にした。
「はい…。」
「俺に聞かれてもなぁ…。」
五十嵐は困ったように頭を掻いた。
「そうだな、俺はいいと思う。だって、俺はお前が好きやぞ。素直でいい奴やと思う。」
不意に五十嵐に褒められ透は素直に嬉しく思った。
こんな風に面と向かって【好き】だと言ってくれた大人はいなかったからだ。
家の中では親は居なく、たまに帰って来たと思えば何かを言うわけでもなく顔を合わせてしまったら溜息ばかり聞かされていた。
ずっと自分自身はこの世で生きていてはいけない物だと思っていた。
だから、あの日アイツを殺して自分も殺すつもりだった。
けれど透は生きる道を選んで今、不謹慎にも生きてきてよかったと思えた。
「だからきっと、舞もお前を気にいるさ。」
そう言ってまた透の頭を撫でた。
今度は素直に五十嵐の手の温もりを受け入れた。
透は考えた。
このモヤモヤした物が恋というのだと知った今自分は何をすればいいのか?
今度何処かに誘う?
いや、それは急過ぎる。
じゃ食事に誘う?
高校生の女の子が好む物がわからない。
けれど、そもそも自分が誰かを好きになって幸せを望む事が許されるのだろうか?
「僕が恋なんてしていいのかな?」
心の想いが口に出た。
「良いに決まってやろ。恋することは生きていれば誰にでも起こる感情なんや。もちろん俺にだってな!だからお前の気持ちは当たり前や。なんせ、俺の姪やからな!」
五十嵐はニカっと笑った。
透は勝手にも五十嵐に言われた言葉が、あの人に言われてる様な気がした。
『いいよ。』って言われた気がした。
「ありがとうございます。僕頑張ってみます。」
「おぉまたなんかあったら、なんでも相談してき。」
五十嵐はそう言ってコーヒーを淹れ透の前に差し出した。
「はい…さっそくなんですが舞さんは何が好きなんですか?食べ物とか、趣味とか…。」
五十嵐はう〜んと首を捻り考えた。
「そや、焼肉は好きやな!この前の焼肉もアイツのリクエストやったからな。あと寿司も好きみたいやぞ。たまに連れてけって催促されるからなぁ。趣味かぁ…趣味なぁ…なんやろな……。友達とはよくカラオケとか映画行ってるみたいやな。たまに見せられるプリクラってやつに、なんかそないな事書いてあった様な気がするわ。」
「映画ですか!?僕も好きです、映画!」
興奮した透の声はうわずった。
透は遊ぶ友達なんてものは一人も居なかった。
殆どの時間、家で過ごしていた透にとってテレビが友達みたいな物だった。
そんな透にとって映画という世界は自分を色んな世界へと連れて行ってくれる魔法みたいな物だった。
毎日何かしら一本は映画を観ていた。
多い時で一日8本観る時もあった。
ジャンル関係なく、どんな作品も観てきた。
ただ弁護士を目指すようになってからは、その時間の全てを勉強に費やしてきたので、ここ数年まともに映画を観ていない。
そろそろ落ち着いてきたから、観に行こうかと思っていたところだった。
「映画誘ってみてもいいでしょうか?」
興奮したまま透は五十嵐に問う。
「俺に聞かれてもなぁ…いっぺん誘ってみたらええんとちゃうか?!もしアイツとお前の休みが合わんねんやったら、都合つけたるから。」
五十嵐の優しさが透を一層興奮させた。
透は五十嵐の手を取りブンブンと上下に揺らした。
「ありがとうございます!!」
「わかったわかった。落ち着け!誘ってみてからの話やろ?!」
「あっはい、電話してみます。」
そう言って透はズボンのポケットから携帯を取り出した。
「おいっ今は仕事中やぞ!」
五十嵐は意地悪で透に告げた。
間に受けた透は慌てて携帯を仕舞う。
それを見た五十嵐は笑った。
五十嵐は透に嘘だと言ったけれど、真面目な透に冗談は冗談にならず、「仕事が終わってからにします。」と、言って仕事を再開した。