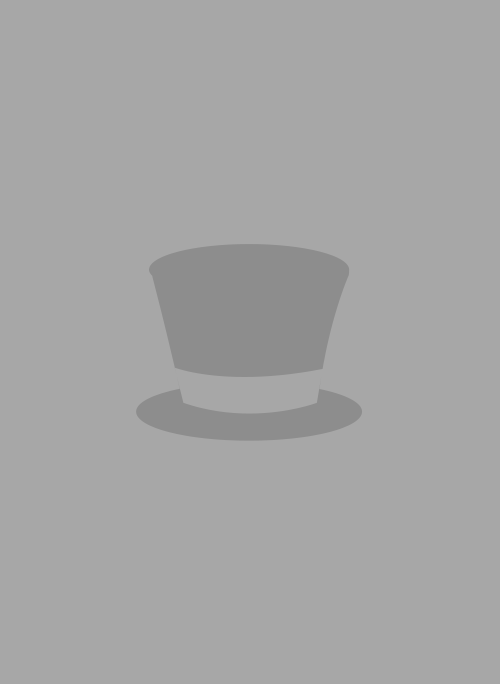あれから12年が経ち少年は27歳の青年へと成長していた。
あの事件は犯人が見つかる事なく未だに未解決とされていた。
あの日大雨だったせいか少年があの場所に居たという形跡は全て流されていた。
証拠は何一つ見つからず一週間もニュースで取り上げられることはなかった。
少年は中学校を卒業し高校受験をしていなかった為、二年間猛勉強し高認を得た。
その後ロースクールに入り法律の全てを叩き込み研修を経て司法試験を受け弁護士となった。
人殺しという過去を隠し自ら選んだ道だった。
多額のお金が必要となったが父親に頭を下げると、変わった息子に喜んだのか快諾した。
少年は命を奪ってしまった五十嵐に懺悔の気持ちを忘れたことはなかった。
いつでも片隅に居て自分がした事を悔いていた。
弁護士を目指した経緯もそこにあった。
勝手かもしれないが、この世から少しでも、あの女の子の様な悲しい想いをしてしまう人を減らしたかった。
警察官とも思ったが父親と同じ仕事だけは避けたかった。
あの人の様な大人にだけはなりたくなかった。
少年は青年になり、周りからチラチラと見られる程の容姿になった。
常に誰かに好意を持たれている。
けれど少年は目もくれず一心に弁護士を目指した。
少年にとって恋や愛という存在しない物は信じる事は出来なかった。
それにまだ少年の世界は色を失ったままだ。
「あの〜いいですか?」
振り返るとそこには14、5歳ぐらいの少女が顔を覗かせていた。
「あっはい。ご相談ですか?」
青年は椅子から腰を上げ少女のもとに駆け寄る。
制服のリボンが、あの日の赤と同じ色をしていた。
青年の頭の中を赤く染める。
「はい…私のことではないんですけど…。」
青年は我に返り、振り払う様に頭を振った。
「はい…お伺いします。こちらへどうぞ。」
青年は少女を席へと案内し、お茶の用意をした。
青年がいる事務所は街の声を聞きたいという所長の希望でこじんまりとした所長と青年しかいない事務所だった。
「どうぞ…今日はどういったご相談ですか?」
「あっありがとうございます。えっと、私の事ではないんですが…友達が嫌がらせというか、ストーカーみたいなのにあっていて…。」
青年は少女の向かいに座った。
「では、一応書類を製作しますので、ご相談者である、貴女の事を教えて頂きたいので、こちらにお願いします。」
青年は少女に書類とペンを渡した。
一通り書き終え渡された書類に目を通す。
少女の名前は《香椎 舞》年齢は17歳だった。
青年は自分の名刺を差し出した。
「深海 透です。宜しくお願いします。」
舞は名刺を受け取り、宜しくお願いしますと返した。
「あの…おじさんは?」
「えっ?」
「あぁ所長さん…私の叔父なんです。」
「えっ?あっそうなんですか?!所長は今日は裁判所で…。」
「あぁそっか。じゃまた日を改めます。」
そう言うと舞は席を立とうとした。
「えっ僕じゃダメですか?話聞きますよ。」
透は慌てて舞を止める。
「ダメじゃないですよ。おじさんなら相談料、無料かなって。」
舞は舌を出し、いたずらっ子の様に笑って見せた。
「相談料は初回無料なので、所長じゃなくても、無料ですよ。」
「なーんだ!」
そう言って舞はまたソファに身を委ねた。
「ではご相談なんですが…。」
透は本題に入った。
すると舞の表情は一変した。
「う…ん。小学校からの友達なんだけど、彼女弱視なんです。見えないわけじゃなくて、ボヤッと見えるぐらいなんですけど、その彼女に高校に入ってから嫌がらせが続いてて…。」
「その嫌がらせとは、どういった内容なんですか?」
透は少し身を乗り出した。
「毎日電話やメールがあって、学校の門で待ってたり、家までついて来たり…。」
「っていうことは香椎さんも見た事あるんですか?」
「はい…何度も。」
「それは…そのお友達のお知り合いなんですか?」
少しの沈黙が流れた。
「…はい。私達の…幼馴染みです。」
言う事を躊躇った理由が透にもわかった。
「それで、強く拒否が出来ずにいるんですね?」
透の言葉が引き金になったのか舞は一気に泣き出した。
透は何も言わず、そっとティッシュを舞の前に置いた。
舞は黙って会釈をし数枚ティッシュを取ると涙を拭いた。
「ごめんなさい…辛いのは私じゃないのに…。」
透は舞のその言葉に驚いた。
透は舞が辛いのだと思っていた。
舞にとっても幼馴染みである彼が友人を傷付けているからだと…。
なのに、舞は友人を想い泣いたのだ。
透にとって誰かを想い泣くなんていう事をした過去がない。
自分には理解出来ない事だと思った。
この先理解する事もない事だと…。
「すみません…泣いたりして…。」
「いや…大丈夫ですよ。」
泣き止んだ舞を見て透は話を再開した。
「当事者であるお友達の話も聞いてみないとはっきりとは言えませんが、その幼馴染みの彼を法的な処置をお考えなんでしょうか?」
「いえ…たぶんそこまでは考えてないというか…したくないです。」
「それは幼馴染みだから?」
「はい…。」
そう答えた舞の瞳は力強く透は言葉に出来ない感情を抱き始めた。
あの事件は犯人が見つかる事なく未だに未解決とされていた。
あの日大雨だったせいか少年があの場所に居たという形跡は全て流されていた。
証拠は何一つ見つからず一週間もニュースで取り上げられることはなかった。
少年は中学校を卒業し高校受験をしていなかった為、二年間猛勉強し高認を得た。
その後ロースクールに入り法律の全てを叩き込み研修を経て司法試験を受け弁護士となった。
人殺しという過去を隠し自ら選んだ道だった。
多額のお金が必要となったが父親に頭を下げると、変わった息子に喜んだのか快諾した。
少年は命を奪ってしまった五十嵐に懺悔の気持ちを忘れたことはなかった。
いつでも片隅に居て自分がした事を悔いていた。
弁護士を目指した経緯もそこにあった。
勝手かもしれないが、この世から少しでも、あの女の子の様な悲しい想いをしてしまう人を減らしたかった。
警察官とも思ったが父親と同じ仕事だけは避けたかった。
あの人の様な大人にだけはなりたくなかった。
少年は青年になり、周りからチラチラと見られる程の容姿になった。
常に誰かに好意を持たれている。
けれど少年は目もくれず一心に弁護士を目指した。
少年にとって恋や愛という存在しない物は信じる事は出来なかった。
それにまだ少年の世界は色を失ったままだ。
「あの〜いいですか?」
振り返るとそこには14、5歳ぐらいの少女が顔を覗かせていた。
「あっはい。ご相談ですか?」
青年は椅子から腰を上げ少女のもとに駆け寄る。
制服のリボンが、あの日の赤と同じ色をしていた。
青年の頭の中を赤く染める。
「はい…私のことではないんですけど…。」
青年は我に返り、振り払う様に頭を振った。
「はい…お伺いします。こちらへどうぞ。」
青年は少女を席へと案内し、お茶の用意をした。
青年がいる事務所は街の声を聞きたいという所長の希望でこじんまりとした所長と青年しかいない事務所だった。
「どうぞ…今日はどういったご相談ですか?」
「あっありがとうございます。えっと、私の事ではないんですが…友達が嫌がらせというか、ストーカーみたいなのにあっていて…。」
青年は少女の向かいに座った。
「では、一応書類を製作しますので、ご相談者である、貴女の事を教えて頂きたいので、こちらにお願いします。」
青年は少女に書類とペンを渡した。
一通り書き終え渡された書類に目を通す。
少女の名前は《香椎 舞》年齢は17歳だった。
青年は自分の名刺を差し出した。
「深海 透です。宜しくお願いします。」
舞は名刺を受け取り、宜しくお願いしますと返した。
「あの…おじさんは?」
「えっ?」
「あぁ所長さん…私の叔父なんです。」
「えっ?あっそうなんですか?!所長は今日は裁判所で…。」
「あぁそっか。じゃまた日を改めます。」
そう言うと舞は席を立とうとした。
「えっ僕じゃダメですか?話聞きますよ。」
透は慌てて舞を止める。
「ダメじゃないですよ。おじさんなら相談料、無料かなって。」
舞は舌を出し、いたずらっ子の様に笑って見せた。
「相談料は初回無料なので、所長じゃなくても、無料ですよ。」
「なーんだ!」
そう言って舞はまたソファに身を委ねた。
「ではご相談なんですが…。」
透は本題に入った。
すると舞の表情は一変した。
「う…ん。小学校からの友達なんだけど、彼女弱視なんです。見えないわけじゃなくて、ボヤッと見えるぐらいなんですけど、その彼女に高校に入ってから嫌がらせが続いてて…。」
「その嫌がらせとは、どういった内容なんですか?」
透は少し身を乗り出した。
「毎日電話やメールがあって、学校の門で待ってたり、家までついて来たり…。」
「っていうことは香椎さんも見た事あるんですか?」
「はい…何度も。」
「それは…そのお友達のお知り合いなんですか?」
少しの沈黙が流れた。
「…はい。私達の…幼馴染みです。」
言う事を躊躇った理由が透にもわかった。
「それで、強く拒否が出来ずにいるんですね?」
透の言葉が引き金になったのか舞は一気に泣き出した。
透は何も言わず、そっとティッシュを舞の前に置いた。
舞は黙って会釈をし数枚ティッシュを取ると涙を拭いた。
「ごめんなさい…辛いのは私じゃないのに…。」
透は舞のその言葉に驚いた。
透は舞が辛いのだと思っていた。
舞にとっても幼馴染みである彼が友人を傷付けているからだと…。
なのに、舞は友人を想い泣いたのだ。
透にとって誰かを想い泣くなんていう事をした過去がない。
自分には理解出来ない事だと思った。
この先理解する事もない事だと…。
「すみません…泣いたりして…。」
「いや…大丈夫ですよ。」
泣き止んだ舞を見て透は話を再開した。
「当事者であるお友達の話も聞いてみないとはっきりとは言えませんが、その幼馴染みの彼を法的な処置をお考えなんでしょうか?」
「いえ…たぶんそこまでは考えてないというか…したくないです。」
「それは幼馴染みだから?」
「はい…。」
そう答えた舞の瞳は力強く透は言葉に出来ない感情を抱き始めた。