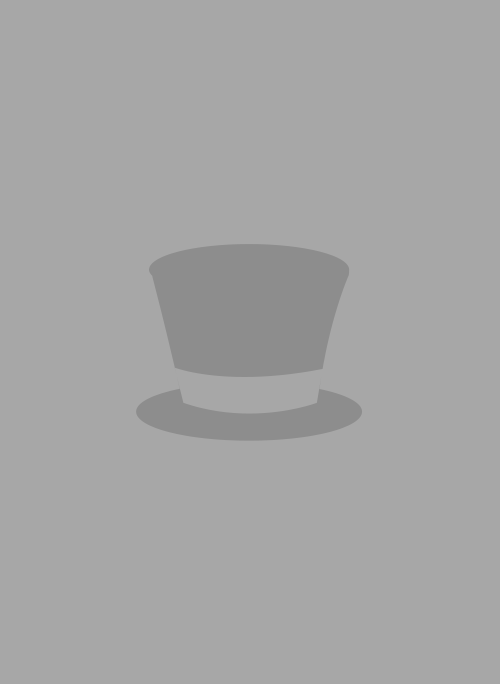こんなに早く目が覚めるなんて、自分でも驚いた。
いつぶりだろう…出かけるのがこんなに楽しみなのは…。
ベッド脇に置かれてる時計を見ると、まだ6時前だった。
静かに寝息を立てて眠る舞を起こさない様に透はベッドから出た。
ふと舞の寝顔を見ると涙の跡がある。
泣いたのか…?
そっと舞の頬に触れようとした時、背後から声がした。
『その女、お前を殺すぞ!』
触れようとした手を引っ込めた。
「舞がそんな事するわけないだろう。」
鏡の中の透はニヤニヤしながら話を進めた。
『いや、そいつは確実にお前を殺す。』
透はもう一度舞を見た。
「その時は僕が殺るさ。」
『さっすがだな。一人殺した人間は何人やろうが一緒ってことか!?』
透は返事を返さず洗面所に向かった。
扉を開けると洗面所の大きな鏡に透が映る。
「その時は…僕が……。」
透は鏡に映る自分と見つめ合い決意するかの様に独り言を言った。
顔洗いタオルで拭きながらリビングに戻った。
横目でベッドを見る。
舞はまだ寝ている。
舞が用意してくれた自分の荷物にそっとソレを忍ばせた。
もし本当に舞が自分を殺そうとしていたとしたら?
僕は…どうしたらいい?
あの日舞の父親を刺した、あの日、事故だったと言えばそれは言い訳にしかならない。
僕は苦痛に顔を歪ませた、あの人をそのままにして逃げた。
そして今まで黙ったまま生きて来たんだ。
言い訳なんて遺族には、意味がない。
それに言い訳するつもりもない。
だから、舞が僕を本当に殺そうとしてたとしても、驚かない。
僕が舞の立場でも同じ事を考える。
けれど僕は殺されたくはないんだ。
勝手だけど、殺されたくはない。
だからその時は…。
小さな声を出しながら舞が目覚めてベッドで伸びをした。
「あれ…もう起きてるの?」
「うん、なんか目覚めてしまって…。」
「そっか…おはよう。」
舞はもう一度伸びをして立ち上がり洗面所に行った。
少ししてから洗面所から舞が声をかけて来た。
「透さーん、コーヒー入れて!」
「うん、今入れてる。」
朝起きると舞は顔を洗いコーヒーを飲む。
さっぱりした顔で舞が戻って来た。
「さすが、透さん。ありがとう。」
「どう致しまして。」
ゆっくりと二人で朝コーヒーを飲むのは幸せだった。
この時間はこれからも舞と分け合いたい時間の一つだ。
「予定より一時間程早くなるけど、8時頃出ようか?」
「うん。わかった。」
舞はコーヒーを飲むと前日から用意していたのか、クローゼットからハンガーに掛けたワンピースを出してきた。
淡いピンク色のそのワンピースは足首まである裾はひらりとさせた。
「それって…」
「買っちゃった。」
そう言って舞は笑った。
やっぱり舞の笑顔は見てるだけで幸せな気持ちになれる。
この笑顔を失いたくはない。
程なくして舞が用意出来たよと、言って来た。
僕はカウンターに置かれた携帯をズボンの後ろポケットに入れ車の鍵を持った。
家の鍵は舞が手に持っていたので僕は家の鍵を鞄に入れた。
自分の鞄と舞の鞄を持って玄関に向かう。
「ありがとう。」
「あっ、うん。」
さらっとありがとうと言えるのも舞の長所だ。
僕にはなかなか難しい事でもある。
言う場面になっても、言わなきゃと思っても何かが邪魔をして喉が詰まる。
ありがとうと言うのも言われる事も見て育たなかった僕にとっては、ハードルの高い言葉になった。
けれど今の事務所に入社してから、わかったんだ。
言う方も言われる方も幸せな気持ちになれる言葉だという事に。
五十嵐さんが教えてくれた、当たり前の世界。
「透さん?聞いてる?」
地下の駐車場に向かうエレベーターの中で舞に顔を覗き込まれた。
「あっごめん。」
「もう!透さんは楽しみじゃないの!?」
舞はぷくっと頬を膨らませた。
「あっ、えーっと…。」
「だから、旅行!!」
さらに膨らませた頬。
そのままふいっとそっぽを向いた。
「ごめんごめん。楽しみにしてるよ。美味しい物食べような。」
「うん。行きたい所はもう調べてるの。」
舞は僕に向き直りニコッと笑って見せた。
色んな所を観光した後、泊まるコテージまでの道程にあるスーパーに立ち寄った。
食事は自分たちでしなくてはいけない。
買い物をして30分程した所に泊まるコテージがあった。
いくつかのコテージが並んでいるが、一棟一棟はそれぞれ離れていて静かな場所だった。
鍵は掛かっておらず、入るとリビングがあり、そこに置かれたテーブルの上に鍵と使用事項の薄い冊子が一冊置かれていた。
奥にはリビングと対面式のキッチンがあり、冷蔵庫と食器棚があり、その中のは事前に聞いた宿泊人数の分の食器が入っていた。
リビングは真ん中は階段があり、テーブルの置かれたダイニングとソファーが置かれたリビングがある。
丁度真ん中の階段が衝立の役割を果たしていた。
「取り敢えず買って来た物、冷蔵庫に入れちゃうね。」
両手にスーパーの袋を下げ舞はキッチンに入って行った。
冷蔵庫に食材を入れた後、二人でソファーでくつろいだ。
「あっビールは?取って来ようか?」
透は立ち上がろうとした舞の腕を掴んだ。
「いや、いいよ。こうしていたい。」
そう言って透はソファーに深く座り足の間に舞を座らせ後ろから抱きしめた。
無言の時間が過ぎて行く。
窓に夕焼けが射し込んで来た。
「透さん?」
「うん?」
「なんかあったの?」
「いや、こうしてたいだけ。ほら、最近忙しくて舞にひっついてなかっただろ?」
「そうね。」
舞は透の言葉にふふっと笑った。
いつぶりだろう…出かけるのがこんなに楽しみなのは…。
ベッド脇に置かれてる時計を見ると、まだ6時前だった。
静かに寝息を立てて眠る舞を起こさない様に透はベッドから出た。
ふと舞の寝顔を見ると涙の跡がある。
泣いたのか…?
そっと舞の頬に触れようとした時、背後から声がした。
『その女、お前を殺すぞ!』
触れようとした手を引っ込めた。
「舞がそんな事するわけないだろう。」
鏡の中の透はニヤニヤしながら話を進めた。
『いや、そいつは確実にお前を殺す。』
透はもう一度舞を見た。
「その時は僕が殺るさ。」
『さっすがだな。一人殺した人間は何人やろうが一緒ってことか!?』
透は返事を返さず洗面所に向かった。
扉を開けると洗面所の大きな鏡に透が映る。
「その時は…僕が……。」
透は鏡に映る自分と見つめ合い決意するかの様に独り言を言った。
顔洗いタオルで拭きながらリビングに戻った。
横目でベッドを見る。
舞はまだ寝ている。
舞が用意してくれた自分の荷物にそっとソレを忍ばせた。
もし本当に舞が自分を殺そうとしていたとしたら?
僕は…どうしたらいい?
あの日舞の父親を刺した、あの日、事故だったと言えばそれは言い訳にしかならない。
僕は苦痛に顔を歪ませた、あの人をそのままにして逃げた。
そして今まで黙ったまま生きて来たんだ。
言い訳なんて遺族には、意味がない。
それに言い訳するつもりもない。
だから、舞が僕を本当に殺そうとしてたとしても、驚かない。
僕が舞の立場でも同じ事を考える。
けれど僕は殺されたくはないんだ。
勝手だけど、殺されたくはない。
だからその時は…。
小さな声を出しながら舞が目覚めてベッドで伸びをした。
「あれ…もう起きてるの?」
「うん、なんか目覚めてしまって…。」
「そっか…おはよう。」
舞はもう一度伸びをして立ち上がり洗面所に行った。
少ししてから洗面所から舞が声をかけて来た。
「透さーん、コーヒー入れて!」
「うん、今入れてる。」
朝起きると舞は顔を洗いコーヒーを飲む。
さっぱりした顔で舞が戻って来た。
「さすが、透さん。ありがとう。」
「どう致しまして。」
ゆっくりと二人で朝コーヒーを飲むのは幸せだった。
この時間はこれからも舞と分け合いたい時間の一つだ。
「予定より一時間程早くなるけど、8時頃出ようか?」
「うん。わかった。」
舞はコーヒーを飲むと前日から用意していたのか、クローゼットからハンガーに掛けたワンピースを出してきた。
淡いピンク色のそのワンピースは足首まである裾はひらりとさせた。
「それって…」
「買っちゃった。」
そう言って舞は笑った。
やっぱり舞の笑顔は見てるだけで幸せな気持ちになれる。
この笑顔を失いたくはない。
程なくして舞が用意出来たよと、言って来た。
僕はカウンターに置かれた携帯をズボンの後ろポケットに入れ車の鍵を持った。
家の鍵は舞が手に持っていたので僕は家の鍵を鞄に入れた。
自分の鞄と舞の鞄を持って玄関に向かう。
「ありがとう。」
「あっ、うん。」
さらっとありがとうと言えるのも舞の長所だ。
僕にはなかなか難しい事でもある。
言う場面になっても、言わなきゃと思っても何かが邪魔をして喉が詰まる。
ありがとうと言うのも言われる事も見て育たなかった僕にとっては、ハードルの高い言葉になった。
けれど今の事務所に入社してから、わかったんだ。
言う方も言われる方も幸せな気持ちになれる言葉だという事に。
五十嵐さんが教えてくれた、当たり前の世界。
「透さん?聞いてる?」
地下の駐車場に向かうエレベーターの中で舞に顔を覗き込まれた。
「あっごめん。」
「もう!透さんは楽しみじゃないの!?」
舞はぷくっと頬を膨らませた。
「あっ、えーっと…。」
「だから、旅行!!」
さらに膨らませた頬。
そのままふいっとそっぽを向いた。
「ごめんごめん。楽しみにしてるよ。美味しい物食べような。」
「うん。行きたい所はもう調べてるの。」
舞は僕に向き直りニコッと笑って見せた。
色んな所を観光した後、泊まるコテージまでの道程にあるスーパーに立ち寄った。
食事は自分たちでしなくてはいけない。
買い物をして30分程した所に泊まるコテージがあった。
いくつかのコテージが並んでいるが、一棟一棟はそれぞれ離れていて静かな場所だった。
鍵は掛かっておらず、入るとリビングがあり、そこに置かれたテーブルの上に鍵と使用事項の薄い冊子が一冊置かれていた。
奥にはリビングと対面式のキッチンがあり、冷蔵庫と食器棚があり、その中のは事前に聞いた宿泊人数の分の食器が入っていた。
リビングは真ん中は階段があり、テーブルの置かれたダイニングとソファーが置かれたリビングがある。
丁度真ん中の階段が衝立の役割を果たしていた。
「取り敢えず買って来た物、冷蔵庫に入れちゃうね。」
両手にスーパーの袋を下げ舞はキッチンに入って行った。
冷蔵庫に食材を入れた後、二人でソファーでくつろいだ。
「あっビールは?取って来ようか?」
透は立ち上がろうとした舞の腕を掴んだ。
「いや、いいよ。こうしていたい。」
そう言って透はソファーに深く座り足の間に舞を座らせ後ろから抱きしめた。
無言の時間が過ぎて行く。
窓に夕焼けが射し込んで来た。
「透さん?」
「うん?」
「なんかあったの?」
「いや、こうしてたいだけ。ほら、最近忙しくて舞にひっついてなかっただろ?」
「そうね。」
舞は透の言葉にふふっと笑った。