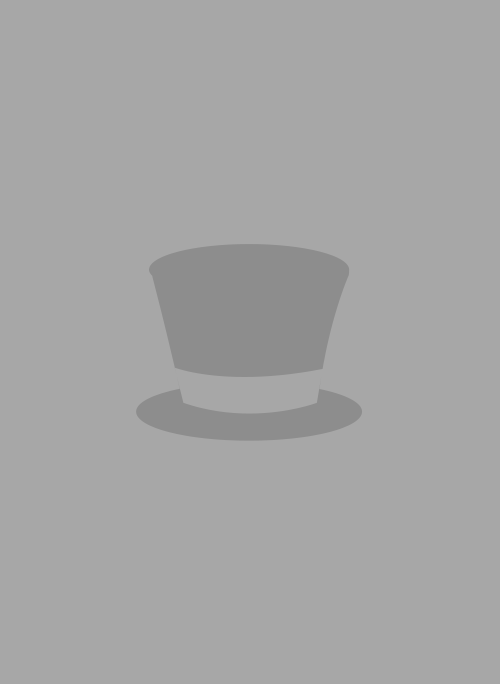次の日、予定通りに二人は買い物に出かけた。
「休んでも大丈夫だったの?」
休憩がてら立ち寄った売店でソフトクリームを食べながら舞が聞いてきた。
「大丈夫だよ。ちゃんと理由言ったし、有給使ったから。」
「叔父さんなんか言ってた?」
「いや、でも舞と一緒に夏休みの間暮らすって言ったら嬉しそうにしてた。」
「そっか。まぁ叔父さんはお父さんの替わりみたいなもんだったからなぁ。」
「ごめん…。」
「もうっ!また…。毎回そんなに謝られると会話出来なくなるじゃん。」
舞はプクッと拗ねて見せた。
「ごめん。少しずつかもしれないけど、慣れる様にするから。」
「よし、休憩終わり!あっちにあった雑貨屋さん行きたいんだけどいい?」
舞は元気よく立って店のある方向を指差した。
「うん。じゃ行こうか。」
二人は腕を組み歩いた。
どこから見ても、誰が見ても二人は仲の良いカップルだった。
夕方になり二人は食事をして帰ることにした。
食事を終え、家に着くと舞は買い物した荷物をさっそく広げ出した。
「もう、遅いし明日にしたら?」
「今したいの。」
そう言って舞はバタバタと楽しそうに動いた。
モノトーンで造られていた空間は舞のモノトーンで華やかになった。
殆ど入っていなかった食器棚はカラフルな食器で埋まり、ベットカバーや枕カバーもカラフルになった。
クッションやカーテンも明るくなった。
なんだか透には少し居心地が悪くなった。
「やっぱり、少し明るくないか?」
頭を掻きながら付け替えたカーテンを見て透が言うと、舞はクスッと笑った。
「それ、叔父さんとおんなじ。」
透は指摘された手を笑いながらおろした。
「それでも我慢したほうなんだけどな…透さんは嫌?」
「ううん、嫌じゃないよ。ただ一気に変わりすぎて戸惑ってるかな。」
「じゃ慣れてくれなきゃね」
「うん、わかったよ。」
舞は買って来たばかりのお揃いのマグカップにコーヒーを淹れた。
「透さん、コーヒー淹れたよ。」
「ありがとう。」
ソファーに座りコーヒーを一口飲んだ。
いつも飲んでいるコーヒーが隣に舞が居るだけで、一段と美味く感じた。
「先にシャワー浴びてきたら?」
透に言われ舞はわかったと、浴室に向かった。
透は浴室に向かった舞の後ろ姿を目で追った。
一緒に誰かと暮らすのも悪くないんだと思っていた。
リビングと廊下を隔てるガラス戸に久しぶりにヤツが姿を見せた。
『なぁ…本気なのか?』
やけに心配そうな声で話しかけてきた。
「なにが?お前には関係のないことだろう。」
『アイツはお前を許してなんかないぞ。自分の親を殺した相手と…なんて気味が悪過ぎだろ!』
確信を突いてくる。
「わかってる…。」
『そっか…殺す隙を伺うって魂胆なんだな!?』
「あぁ。」
心にも無い事を口にしたと透は思った。
けれど、口にしたとたん、妙に真実身を帯びた気がした。
『ならいい…オレは静かに見学させてもらうとするかな!?』
そう言って口元をいつも通り歪ませ消えた。
透は空になったマグカップを流しに置くと カウンターに置かれたパソコンを開いた。
これといって舞に見られて困る物はないが確認をする必要があった。
舞の隠し事はない。
もう全てを伝えた。
けれど、なんとなくパソコンは自分の全てが入ってる感じがしてるせいか見られたくない気もする。
一通り見たけれど、やっぱり何もやましい事はない。
ただ仕事の事やクライアントの事などにはロックを掛けた。
パソコンを閉じようとした時ガラス戸が開き舞が戻って来た。
やっぱり何度見ても、あの長く伸びた黒髪にドキッとしてしまう。
「何?お仕事?」
パソコンに手をかけていた透を見て舞は声を掛けた。
「いや…クライアントの資料とかにロックを掛けたんだ。間違って開かないように…。」
「やだぁ、そんな事しなくてもパソコン触らないよ。」
舞は笑いながら言った。
「あっそうなの?」
「うん。」
「そっか…。」
「あーわかった!」
急に大声で言われ体がビクっとなった。
「エッチなの消してたんでしょ〜?」
「そんなのないよ!!」
「あっやし〜〜!」
舞は透の頭をくしゃくしゃにして戯れた。
「休んでも大丈夫だったの?」
休憩がてら立ち寄った売店でソフトクリームを食べながら舞が聞いてきた。
「大丈夫だよ。ちゃんと理由言ったし、有給使ったから。」
「叔父さんなんか言ってた?」
「いや、でも舞と一緒に夏休みの間暮らすって言ったら嬉しそうにしてた。」
「そっか。まぁ叔父さんはお父さんの替わりみたいなもんだったからなぁ。」
「ごめん…。」
「もうっ!また…。毎回そんなに謝られると会話出来なくなるじゃん。」
舞はプクッと拗ねて見せた。
「ごめん。少しずつかもしれないけど、慣れる様にするから。」
「よし、休憩終わり!あっちにあった雑貨屋さん行きたいんだけどいい?」
舞は元気よく立って店のある方向を指差した。
「うん。じゃ行こうか。」
二人は腕を組み歩いた。
どこから見ても、誰が見ても二人は仲の良いカップルだった。
夕方になり二人は食事をして帰ることにした。
食事を終え、家に着くと舞は買い物した荷物をさっそく広げ出した。
「もう、遅いし明日にしたら?」
「今したいの。」
そう言って舞はバタバタと楽しそうに動いた。
モノトーンで造られていた空間は舞のモノトーンで華やかになった。
殆ど入っていなかった食器棚はカラフルな食器で埋まり、ベットカバーや枕カバーもカラフルになった。
クッションやカーテンも明るくなった。
なんだか透には少し居心地が悪くなった。
「やっぱり、少し明るくないか?」
頭を掻きながら付け替えたカーテンを見て透が言うと、舞はクスッと笑った。
「それ、叔父さんとおんなじ。」
透は指摘された手を笑いながらおろした。
「それでも我慢したほうなんだけどな…透さんは嫌?」
「ううん、嫌じゃないよ。ただ一気に変わりすぎて戸惑ってるかな。」
「じゃ慣れてくれなきゃね」
「うん、わかったよ。」
舞は買って来たばかりのお揃いのマグカップにコーヒーを淹れた。
「透さん、コーヒー淹れたよ。」
「ありがとう。」
ソファーに座りコーヒーを一口飲んだ。
いつも飲んでいるコーヒーが隣に舞が居るだけで、一段と美味く感じた。
「先にシャワー浴びてきたら?」
透に言われ舞はわかったと、浴室に向かった。
透は浴室に向かった舞の後ろ姿を目で追った。
一緒に誰かと暮らすのも悪くないんだと思っていた。
リビングと廊下を隔てるガラス戸に久しぶりにヤツが姿を見せた。
『なぁ…本気なのか?』
やけに心配そうな声で話しかけてきた。
「なにが?お前には関係のないことだろう。」
『アイツはお前を許してなんかないぞ。自分の親を殺した相手と…なんて気味が悪過ぎだろ!』
確信を突いてくる。
「わかってる…。」
『そっか…殺す隙を伺うって魂胆なんだな!?』
「あぁ。」
心にも無い事を口にしたと透は思った。
けれど、口にしたとたん、妙に真実身を帯びた気がした。
『ならいい…オレは静かに見学させてもらうとするかな!?』
そう言って口元をいつも通り歪ませ消えた。
透は空になったマグカップを流しに置くと カウンターに置かれたパソコンを開いた。
これといって舞に見られて困る物はないが確認をする必要があった。
舞の隠し事はない。
もう全てを伝えた。
けれど、なんとなくパソコンは自分の全てが入ってる感じがしてるせいか見られたくない気もする。
一通り見たけれど、やっぱり何もやましい事はない。
ただ仕事の事やクライアントの事などにはロックを掛けた。
パソコンを閉じようとした時ガラス戸が開き舞が戻って来た。
やっぱり何度見ても、あの長く伸びた黒髪にドキッとしてしまう。
「何?お仕事?」
パソコンに手をかけていた透を見て舞は声を掛けた。
「いや…クライアントの資料とかにロックを掛けたんだ。間違って開かないように…。」
「やだぁ、そんな事しなくてもパソコン触らないよ。」
舞は笑いながら言った。
「あっそうなの?」
「うん。」
「そっか…。」
「あーわかった!」
急に大声で言われ体がビクっとなった。
「エッチなの消してたんでしょ〜?」
「そんなのないよ!!」
「あっやし〜〜!」
舞は透の頭をくしゃくしゃにして戯れた。