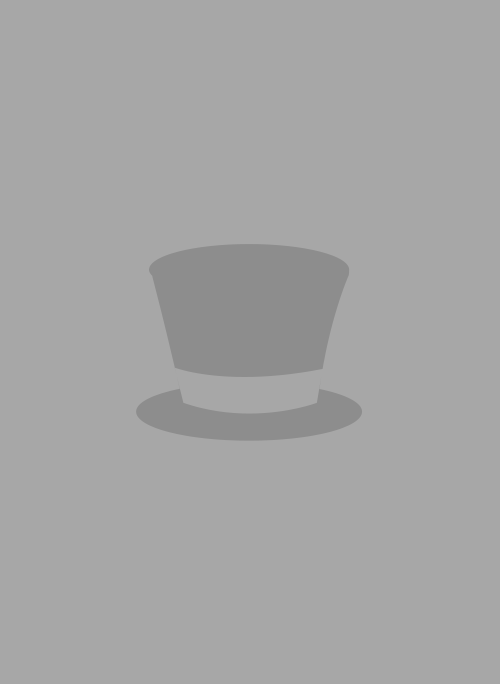ボクがキミに出会ったのは、キミが4歳を迎えた雪降る日だった。
家の中は暖かくて外は雪が降ってることを忘れる程だった。
パパさんがボクを女の子に会わせてくれたんだ。
「アタシ希華っていうの。よろしくね。」
その女の子はボクに話しかけてきた。
“いちか”と言ったキミ名前はボクの心を温かくしたんだ。
「アナタのお名前は?」
ボクの名前…??
「クーちゃん。アナタのお名前クーちゃんね。」
ボクはキミが4歳になった日にクーちゃんとなった。
その日からボクはどんな時もいろんな時間をキミと過ごした。
ごはんを食べる時も、テレビを見る時も、寝る時も、公園に行く時も、いつだって一緒に居たんだ。
けれど朝から昼過ぎまではキミは幼稚園って所に行ってしまってボクは一人だった。
キミのベットで窓から外を見つめ、いつもキミの帰りを待っていた。
キミは帰って来たら真っ先にボクに「クーちゃん、ただいま。」と言ってくれるんだ。
小学生になる頃、キミは少し背も伸び髪も伸び二つに結んで赤いランドセルを背負って毎朝家を出て行った。
初めてランドセルを手にした時は毎日ボクに見せてくれた。
「クーちゃん見て見て。4月になったら小学校ってとこに行くんだよ。アタシ一年生になるの。」
毎日聞かされる、その台詞は飽きることなく、嬉しそうに話してくれる笑顔を見てボクも嬉しかったんだ。
学校生活が始まってキミは毎日学校で起こった事を報告してくれたね。
「今日あっちゃんがね…」
「今日国語でね…」
どの話もボクには想像つかなかったけれど、キミが嬉しそうに話すからボクはそれだけで幸せだったんだ。
季節が暑くなってきた頃、キミが学校に行かなくなった。
毎日家に居て、毎日にボクと遊んだ。
パパさんとママさんと希華ちゃんと海ってとこにも行った。
どこまでも続く砂場があった。
公園の砂場とは比べ物にもならない程広い広い砂場が続いていたんだ。
その先にはキラキラ光る大きな水溜り。
「クーちゃん、あれが海っていうのよ。」
希華ちゃんはボクにそう言って、その海へと走って行った。
大きな傘の下でママさんと一緒に、パパさんとはしゃぐ希華ちゃんを見ていた。
キミの世界でいう夏休みだという事を、夏休みが終わる頃知った。
「もうすぐ夏休み終わっちゃう。」
そう言ってキミは寂しそうにボクに抱きついた。
そんなに寂しいのかと思った。
「学校行ってる間クーちゃんと一緒にいれないね。」
ボクの事を想ってたの??
嬉しかった。
涙というものはボクにはないけど、あるならきっと流れてると思った。
程なくしてまたキミは学校に行ってしまった。
秋になる頃キミの様子が少し変わったように感じた。
いつものように学校から帰って来て、いつものようにテレビ見て、いつものようにごはんを食べた。
けれど、ボクが感じた違和感は間違いじゃなかった。
寝ようといつも通りにボクとベットに入った。
キミはいつも少しボクに話しかけてきてから眠りにつくのに、その日はずっと黙ったままボクを抱きしめてた。
それになかなか寝ようとしない。
気になってボクは耳を澄ました。
寝息にもならない。
「クーちゃん…アタシね…好きな男の子できちゃったの。」
好きな男の子…??
確か幼稚園の時も〜くん好きって言ってた。
いや、あの時と少し違う感じがする。
「隣のクラスの男の子なんだけどね。今日廊下で違う男子とぶつかった時、大丈夫?って起こしてくれたの。」
そう言って希華は恥ずかしそうにした。
幼稚園の時とは明らかに違う表情だった。
「でも隣のクラスだし、名前わかんないし…。」
次は寂しそうな表情。
「クーちゃん…アタシどうしよう。」
そんな事言われてもボクは学校に行けないよ。
「クーちゃんに言っても仕方がないよね。」
何故だか心がズキンとした。
思っていても、わかっていても、希華ちゃんに言われると悲しくなる。
「名前なんていうんだろう…。」
希華ちゃんは呟くように言って落ちていく様に眠りに就いた。
家の中は暖かくて外は雪が降ってることを忘れる程だった。
パパさんがボクを女の子に会わせてくれたんだ。
「アタシ希華っていうの。よろしくね。」
その女の子はボクに話しかけてきた。
“いちか”と言ったキミ名前はボクの心を温かくしたんだ。
「アナタのお名前は?」
ボクの名前…??
「クーちゃん。アナタのお名前クーちゃんね。」
ボクはキミが4歳になった日にクーちゃんとなった。
その日からボクはどんな時もいろんな時間をキミと過ごした。
ごはんを食べる時も、テレビを見る時も、寝る時も、公園に行く時も、いつだって一緒に居たんだ。
けれど朝から昼過ぎまではキミは幼稚園って所に行ってしまってボクは一人だった。
キミのベットで窓から外を見つめ、いつもキミの帰りを待っていた。
キミは帰って来たら真っ先にボクに「クーちゃん、ただいま。」と言ってくれるんだ。
小学生になる頃、キミは少し背も伸び髪も伸び二つに結んで赤いランドセルを背負って毎朝家を出て行った。
初めてランドセルを手にした時は毎日ボクに見せてくれた。
「クーちゃん見て見て。4月になったら小学校ってとこに行くんだよ。アタシ一年生になるの。」
毎日聞かされる、その台詞は飽きることなく、嬉しそうに話してくれる笑顔を見てボクも嬉しかったんだ。
学校生活が始まってキミは毎日学校で起こった事を報告してくれたね。
「今日あっちゃんがね…」
「今日国語でね…」
どの話もボクには想像つかなかったけれど、キミが嬉しそうに話すからボクはそれだけで幸せだったんだ。
季節が暑くなってきた頃、キミが学校に行かなくなった。
毎日家に居て、毎日にボクと遊んだ。
パパさんとママさんと希華ちゃんと海ってとこにも行った。
どこまでも続く砂場があった。
公園の砂場とは比べ物にもならない程広い広い砂場が続いていたんだ。
その先にはキラキラ光る大きな水溜り。
「クーちゃん、あれが海っていうのよ。」
希華ちゃんはボクにそう言って、その海へと走って行った。
大きな傘の下でママさんと一緒に、パパさんとはしゃぐ希華ちゃんを見ていた。
キミの世界でいう夏休みだという事を、夏休みが終わる頃知った。
「もうすぐ夏休み終わっちゃう。」
そう言ってキミは寂しそうにボクに抱きついた。
そんなに寂しいのかと思った。
「学校行ってる間クーちゃんと一緒にいれないね。」
ボクの事を想ってたの??
嬉しかった。
涙というものはボクにはないけど、あるならきっと流れてると思った。
程なくしてまたキミは学校に行ってしまった。
秋になる頃キミの様子が少し変わったように感じた。
いつものように学校から帰って来て、いつものようにテレビ見て、いつものようにごはんを食べた。
けれど、ボクが感じた違和感は間違いじゃなかった。
寝ようといつも通りにボクとベットに入った。
キミはいつも少しボクに話しかけてきてから眠りにつくのに、その日はずっと黙ったままボクを抱きしめてた。
それになかなか寝ようとしない。
気になってボクは耳を澄ました。
寝息にもならない。
「クーちゃん…アタシね…好きな男の子できちゃったの。」
好きな男の子…??
確か幼稚園の時も〜くん好きって言ってた。
いや、あの時と少し違う感じがする。
「隣のクラスの男の子なんだけどね。今日廊下で違う男子とぶつかった時、大丈夫?って起こしてくれたの。」
そう言って希華は恥ずかしそうにした。
幼稚園の時とは明らかに違う表情だった。
「でも隣のクラスだし、名前わかんないし…。」
次は寂しそうな表情。
「クーちゃん…アタシどうしよう。」
そんな事言われてもボクは学校に行けないよ。
「クーちゃんに言っても仕方がないよね。」
何故だか心がズキンとした。
思っていても、わかっていても、希華ちゃんに言われると悲しくなる。
「名前なんていうんだろう…。」
希華ちゃんは呟くように言って落ちていく様に眠りに就いた。