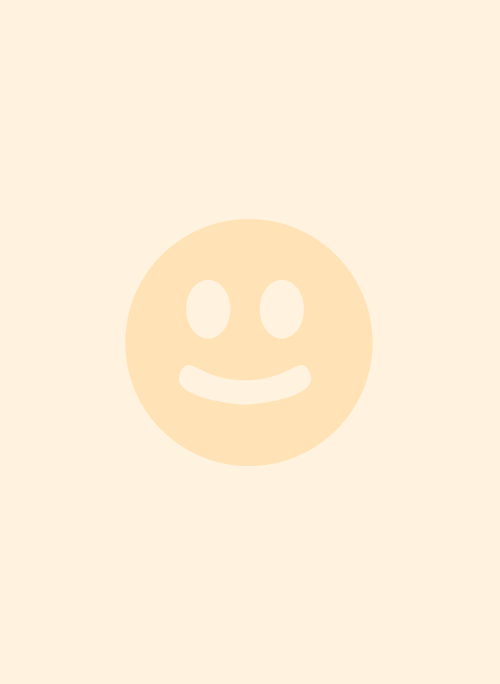サイレンが公園脇の植え込みで停まった。
見覚えのある白黒の鉄の塊に、車輪がついているアレだ。
公園に到着した警官二人が、パトカーから降りて又四郎に近づいて行く。
「君、未成年だね?昼間から公園で素振の練習かい?甲子園行きたいなら、学校に行こうね・・・。」
警官が優しく問いかける。
完全に無視する又四郎。
警官には目もくれず、居合の鍛錬を続ける。
「おい、君!聞いているのか?」
警官は、素振りを制止させるように又四郎の肩に触れようとした。
又四郎は例のごとく気配を察し、触れらる前に蹴りを繰り出そうとしたが、公園の砂利に軸足を取られ、思わず体勢を崩し、きれいにコケる。
「うわっ!」
警官の顔面スレスレを又四郎の足が霞める。
又四郎は空転し、後方へ着地する。
次の攻撃に備え、体勢を立て直す。
「こら!又四郎!!」
聞き覚えのある怒号が響く。
「着物を来た、バットを持った若い不審者が居ると通報が在って、もしかしたらと来てみたらやっぱりお前か!」
更にパトカーから出てきたのは、忠明だった。
「わしに触れようとするくせ者は、倒すのみだ。」
又四郎は忠明に言う。
「くせ者はお前だ!」
忠明と又四郎は一緒にパトカーに乗り、警察署へ向かった。
車中では又四郎をしかりつける忠明と、聞く耳すら持たない又四郎とのやり取りが続いた。
未だに又四郎が江戸時代からタイムトラベルしてきた事に納得と理解ができない忠明は、これ以上騒ぎが起きないよう、万が一に備え、今日の間だけ警察の剣道場に又四郎を預ける事にした。
「いいか、又四郎!騒ぎを起こすなよ!頼むぞ!」
そう言い残し、忠明は職務に戻る。
又四郎は剣道場に一人、佇む。
居心地が良い。
気持ちが落ち着く。
素振り用の重い木刀を二本握り、素振を始める。
淡々と、黙々と。
暫くすると、
警察の剣道を指導する師範が姿を表す。
齢七五歳。千葉周一。(ちばしゅういち)
近代剣道の礎を築いた千葉周作の孫である。
千葉周一は高柳又四郎の素振を見て驚嘆した。
現代には存在しない侍の姿が道場に在ったからだ。
「御仁。私とお手合わせお願いできますかな。」
七五歳の周一は、若者のようにときめいた。
剣道をやって初めてと言って良い感覚が、高柳又四郎を見て、沸々と沸き上がってくる感覚。
又四郎は素振の手を休めて、周一と向き合う。
周一は若い侍の凛とした張り詰めたような気迫に、思わず息を飲む。
同時に、憧れと剣客としての本能から呼び覚まされる興奮を禁じ得ない。
「良かろう、ご老人。拙者は何人であろうと、容赦はせぬ。死ぬ気で掛かって参れ。」
見た目は15才の老練な侍は、周一の想いを受け止めた。
お互いに防具は使用せず、一本打撃が決まった方の勝ち。
古式の出稽古、他流試合の流儀である。
二人は竹刀に持ち変え、正眼で対峙する。