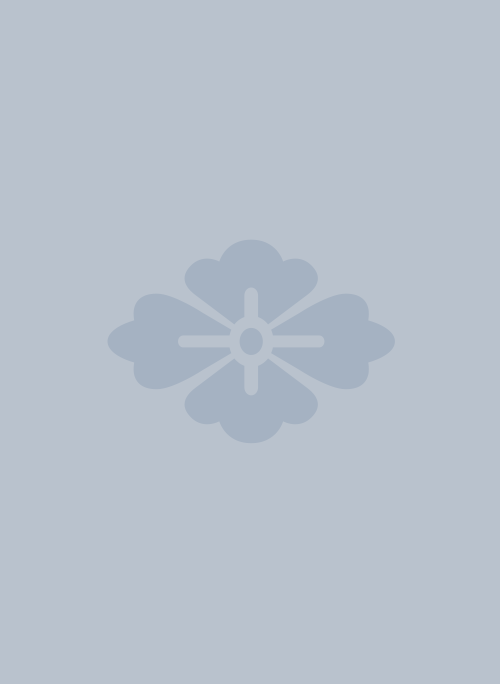「なな、何で貫七さんを苛めるのと関係あるのよ」
「おりんは俺の相棒だ。俺を苛めること即ち、おりんを苛めることだ」
「そ、そんなこと。大体別に、あたしゃ貫七さんを苛めてなんか……」
「毎晩十分苛めてるじゃねぇか。そろそろ肌を許してくれてもいいんじゃねぇかい?」
この上なく美麗な男に至近距離で言われ、お紺は瞬間的に真っ赤になる。
だが。
「いてっ!」
お紺が何か言う前に、貫七の頬に猫パンチが入った。
驚いたお紺の目の前で、おりんが後足で立ち上がり、思い切り振りかぶった前足で、すぐ横の貫七の頬を張ったのだ。
その姿たるや、一瞬後にお紺が取っていたであろう姿にそっくりだ。
つまり、人が思い切り振りかぶって、相手を引っ叩く格好そのもの。
---やっぱりおりん、普通じゃない---
そうは思うが、何故だか恐怖は感じないのだ。
お紺はがばっと貫七からおりんを奪った。
ぎゅぎゅっと抱き締める。
「可愛い~~。ありがとう、おりん~」
いくら行動が人のようだとはいえ、抱き付いてみれば、やはりもふもふの毛皮だ。
猫独特の柔軟さで、おりんは少し身を捩った。
いきなり抱き締められて驚いたようだが、やがてお紺の胸で大人しくなる。
「何だよ。抱き付くなら俺にしなよ」
わけのわからない文句を垂れながら、貫七が頬をさする。
べぇっとお紺は、貫七に向かって舌を突き出した。
「おりんは俺の相棒だ。俺を苛めること即ち、おりんを苛めることだ」
「そ、そんなこと。大体別に、あたしゃ貫七さんを苛めてなんか……」
「毎晩十分苛めてるじゃねぇか。そろそろ肌を許してくれてもいいんじゃねぇかい?」
この上なく美麗な男に至近距離で言われ、お紺は瞬間的に真っ赤になる。
だが。
「いてっ!」
お紺が何か言う前に、貫七の頬に猫パンチが入った。
驚いたお紺の目の前で、おりんが後足で立ち上がり、思い切り振りかぶった前足で、すぐ横の貫七の頬を張ったのだ。
その姿たるや、一瞬後にお紺が取っていたであろう姿にそっくりだ。
つまり、人が思い切り振りかぶって、相手を引っ叩く格好そのもの。
---やっぱりおりん、普通じゃない---
そうは思うが、何故だか恐怖は感じないのだ。
お紺はがばっと貫七からおりんを奪った。
ぎゅぎゅっと抱き締める。
「可愛い~~。ありがとう、おりん~」
いくら行動が人のようだとはいえ、抱き付いてみれば、やはりもふもふの毛皮だ。
猫独特の柔軟さで、おりんは少し身を捩った。
いきなり抱き締められて驚いたようだが、やがてお紺の胸で大人しくなる。
「何だよ。抱き付くなら俺にしなよ」
わけのわからない文句を垂れながら、貫七が頬をさする。
べぇっとお紺は、貫七に向かって舌を突き出した。