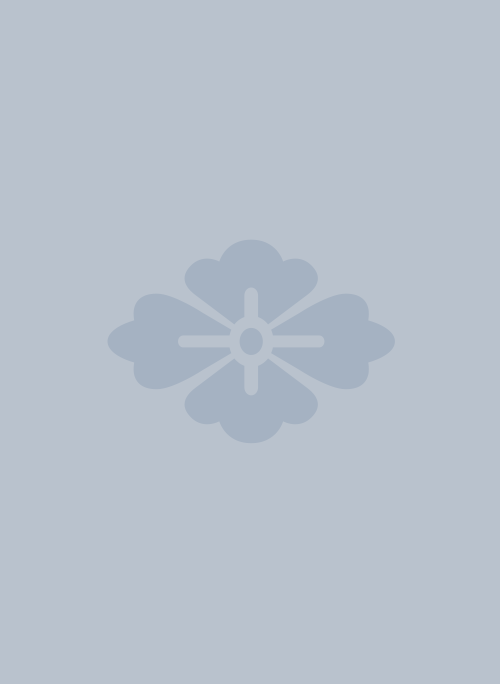「全くお由さんは口が悪いねぇ。俺だって自分が他人に与える影響を十分わかってるから、用心棒はもっぱらおりんに頼んでるんじゃねぇかい」
肩の上のおりんを撫でながら、貫七が言う。
おりんはおりんで、仕事を押し付けられるのは多少不満なものの、貫七の言うことには甘いようだ。
飼い主だからだろうか……。
「おりんはほんとに、貫七さんに懐いてるねぇ」
先程お由を威嚇したのも、彼女が貫七を悪く言ったからだ。
感心したように言うお紺に、おりんは少し小首を傾げた。
こういうところが、こちらの言うことがわかっているのかと思う所以だ。
「ま、相棒だからなぁ」
曖昧に笑いながら、貫七がちらりとおりんを見る。
それに応えるように、肩の上で、おりんはこくりと頷いた。
やはり、会話している。
「おりんはよく働いてくれるけど、ちょっと不気味じゃね」
お由がそんな貫七とおりんを見つつ、ずばりと言う。
お紺は慌ててお由の口を塞いだ。
だが貫七は、そんなお由の感想など、軽く笑い飛ばす。
「はは。違いねぇ。何と言っても、おりんは化け猫だからな」
「ば、化け猫?」
「そうさ。俺を苛めたら、呪われるぜ」
にやにや笑いながら、貫七は、ずいっとお紺に顔を近づける。
肩の上のおりんを撫でながら、貫七が言う。
おりんはおりんで、仕事を押し付けられるのは多少不満なものの、貫七の言うことには甘いようだ。
飼い主だからだろうか……。
「おりんはほんとに、貫七さんに懐いてるねぇ」
先程お由を威嚇したのも、彼女が貫七を悪く言ったからだ。
感心したように言うお紺に、おりんは少し小首を傾げた。
こういうところが、こちらの言うことがわかっているのかと思う所以だ。
「ま、相棒だからなぁ」
曖昧に笑いながら、貫七がちらりとおりんを見る。
それに応えるように、肩の上で、おりんはこくりと頷いた。
やはり、会話している。
「おりんはよく働いてくれるけど、ちょっと不気味じゃね」
お由がそんな貫七とおりんを見つつ、ずばりと言う。
お紺は慌ててお由の口を塞いだ。
だが貫七は、そんなお由の感想など、軽く笑い飛ばす。
「はは。違いねぇ。何と言っても、おりんは化け猫だからな」
「ば、化け猫?」
「そうさ。俺を苛めたら、呪われるぜ」
にやにや笑いながら、貫七は、ずいっとお紺に顔を近づける。