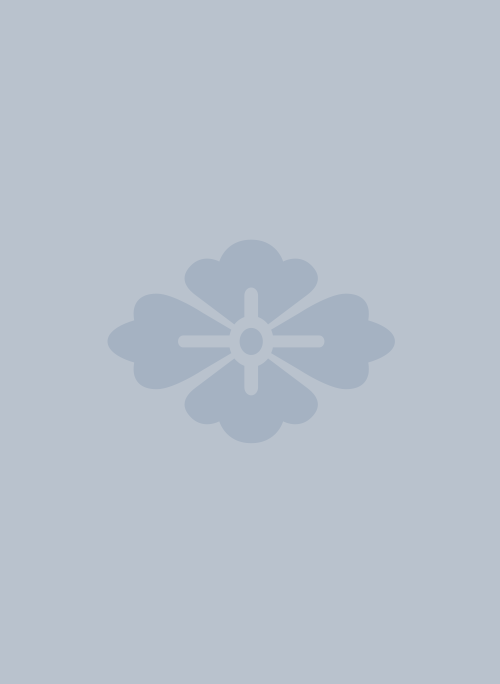「ま、全くよく動く口なんだから! くれぐれも、うちの客に手ぇ出すようなことは、やめておくれよ。そういう店だと思われちゃ適わないからね!」
「いつでも俺から動くことなんかないんだぜ? 動いてもねぇのに、向こうから寄ってくるんだ。手ぇ出してるわけじゃねぇ」
これまたしゃあしゃあと言ってのける。
事実、たまにある女性客の前にこの男が姿を現せば、たちまち虜になってしまう。
まさに老若男女問わずだ。
しかもこいつも、それを十分心得ていて、それなりに楽しむのだ。
案の定、そこに通りがかりの老婆がやってきた。
大きな籠を背負っている。
行商の者だろう。
しわしわだが、店先に佇む男に目をやった途端、老婆は急に、しゃきんと腰を伸ばした。
そそくさと、身なりも整えたりしている。
「ちゃ、茶屋かえ。お茶を頂こうかね」
いそいそと、店先の椅子に腰かける。
そして、男を眩しそうに見上げた。
「兄さん。あんたぁ、何ていうんだい」
そわそわと声をかける老婆にも、男は爽やかな笑顔で応ずる。
「貫七(かんしち)と申します。ようこそ、いらっしゃいました。お疲れでしょう、すぐに茶をお持ちします」
笑顔を向けられた老婆が、ほぉっとしている前で、男---貫七は当たり前のように、お紺に茶を出すよう命じる。
まるで貫七のほうが、この店の主のようだ。
実際はただの居候なのだが。
「いつでも俺から動くことなんかないんだぜ? 動いてもねぇのに、向こうから寄ってくるんだ。手ぇ出してるわけじゃねぇ」
これまたしゃあしゃあと言ってのける。
事実、たまにある女性客の前にこの男が姿を現せば、たちまち虜になってしまう。
まさに老若男女問わずだ。
しかもこいつも、それを十分心得ていて、それなりに楽しむのだ。
案の定、そこに通りがかりの老婆がやってきた。
大きな籠を背負っている。
行商の者だろう。
しわしわだが、店先に佇む男に目をやった途端、老婆は急に、しゃきんと腰を伸ばした。
そそくさと、身なりも整えたりしている。
「ちゃ、茶屋かえ。お茶を頂こうかね」
いそいそと、店先の椅子に腰かける。
そして、男を眩しそうに見上げた。
「兄さん。あんたぁ、何ていうんだい」
そわそわと声をかける老婆にも、男は爽やかな笑顔で応ずる。
「貫七(かんしち)と申します。ようこそ、いらっしゃいました。お疲れでしょう、すぐに茶をお持ちします」
笑顔を向けられた老婆が、ほぉっとしている前で、男---貫七は当たり前のように、お紺に茶を出すよう命じる。
まるで貫七のほうが、この店の主のようだ。
実際はただの居候なのだが。