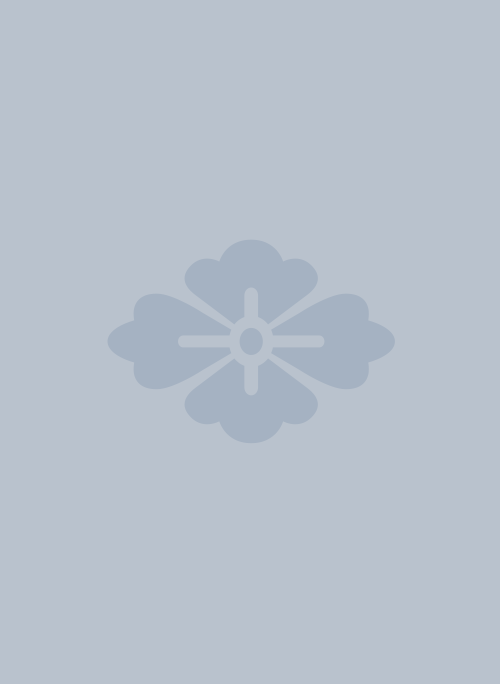「……け、けど俺は、おりんが女だって知らなかったし。俺には衆道の気(け)はねぇよ! おかしいじゃねぇか」
むきになる貫七の膝で、おりんはじっと目を閉じていた。
「知らなかったのは本当じゃろう。でもお前もわしが育てたんじゃぞ。天狗の太郎坊に育てられれば、感覚は人とは段違いに研ぎ澄まされる。わしもそう仕込んだしの。ヒトの中の気を見抜くことも出来るじゃろ。意識して見ていたわけではないから、おりんに関しては気付かなかっただけじゃ。でも何となく、おりんの気も己の心も感じていたじゃろ? 違うか?」
「……」
赤い顔がやたらと熱を持ち、汗が吹き出す。
反論出来ず、貫七は視線を落とした。
その目が、膝の上のおりんの目と合う。
「……っお、おりんっ!!」
大きく仰け反り、貫七が叫ぶ。
おりんは、そろりと起き上がった。
「おや、起きたか。まぁ頭を乗せておる貫七が騒ぎ過ぎたしのぅ」
誰のせいなんだか、とジト目を送る貫七をさらっと無視し、太郎坊は出来た粥を木の器に取った。
「ほれ。お前の好きじゃった芋粥じゃ。ヒトの飯は久しぶりじゃろ」
太郎坊に渡された器を受け取り、おりんはふぅふぅと息を吹きかける。
「ところで。お前たちも無事に戻って来たことじゃし、わしもそろそろ隠居しようかのぅ」
「い、隠居?」
この山奥から、これ以上どこに隠居しようというのか。
貫七は妙な顔で太郎坊を見た。
むきになる貫七の膝で、おりんはじっと目を閉じていた。
「知らなかったのは本当じゃろう。でもお前もわしが育てたんじゃぞ。天狗の太郎坊に育てられれば、感覚は人とは段違いに研ぎ澄まされる。わしもそう仕込んだしの。ヒトの中の気を見抜くことも出来るじゃろ。意識して見ていたわけではないから、おりんに関しては気付かなかっただけじゃ。でも何となく、おりんの気も己の心も感じていたじゃろ? 違うか?」
「……」
赤い顔がやたらと熱を持ち、汗が吹き出す。
反論出来ず、貫七は視線を落とした。
その目が、膝の上のおりんの目と合う。
「……っお、おりんっ!!」
大きく仰け反り、貫七が叫ぶ。
おりんは、そろりと起き上がった。
「おや、起きたか。まぁ頭を乗せておる貫七が騒ぎ過ぎたしのぅ」
誰のせいなんだか、とジト目を送る貫七をさらっと無視し、太郎坊は出来た粥を木の器に取った。
「ほれ。お前の好きじゃった芋粥じゃ。ヒトの飯は久しぶりじゃろ」
太郎坊に渡された器を受け取り、おりんはふぅふぅと息を吹きかける。
「ところで。お前たちも無事に戻って来たことじゃし、わしもそろそろ隠居しようかのぅ」
「い、隠居?」
この山奥から、これ以上どこに隠居しようというのか。
貫七は妙な顔で太郎坊を見た。