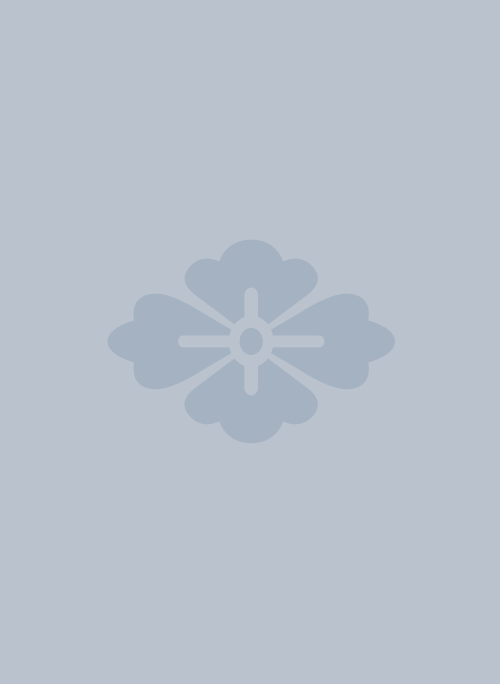「お、お嬢さんっ」
連れが慌てて、娘を助け起こす。
が、娘はぐったりと、目を閉じたままだ。
「お嬢さんってことぁ、こいつはそれなりの家の娘さんってことかい。だったら疲れだろうさ」
貫七が、耳聡く男の言葉から娘の身分を言い当てる。
そして、ちらりとお紺を見た。
「熱があるかもしれん。お紺ちゃん、奥の部屋に布団敷いてやるかい?」
「そ、そうね。じゃあ、こっちに」
お紺が襖を開け、奥の小さな部屋に入った。
そして布団を敷き、客人に手招きする。
「いいとこのお嬢さんを寝かすにゃ、お粗末かもしれませんがねぇ」
お紺が恐縮して言うのを、連れは、いやいや、と遮った。
だが娘を連れて行くのは躊躇っているようだ。
ただそれは、『お嬢さん』に触れるのを躊躇っているだけのようで、だから奥の部屋まで運ぶことが出来ない、という理由のようだが。
「何を躊躇ってんでぃ。すでにお前さん、娘さんに触れてるじゃねぇか」
そんな初心(うぶ)な歳でもあるまいに、と、貫七が呆れ気味に言う。
すると連れは、また慌てて娘を支えていた手を離した。
「おい! 危ねぇ!」
いきなり連れが手を離したため、がくりと倒れる娘に駆け寄った貫七が怒鳴る。
「あんたが連れて行けないってんなら、俺が連れてくぜ」
言うなり貫七は、ひょい、と娘を抱き上げた。
そのままさっさと、奥に運ぶ。
しばし呆けていた連れは、やっと我に返ったように、急いで後を追って来た。
「んじゃあお紺ちゃん、後は頼むぜ」
娘を寝かせ、貫七はさっさと階段を上がって行った。
連れが慌てて、娘を助け起こす。
が、娘はぐったりと、目を閉じたままだ。
「お嬢さんってことぁ、こいつはそれなりの家の娘さんってことかい。だったら疲れだろうさ」
貫七が、耳聡く男の言葉から娘の身分を言い当てる。
そして、ちらりとお紺を見た。
「熱があるかもしれん。お紺ちゃん、奥の部屋に布団敷いてやるかい?」
「そ、そうね。じゃあ、こっちに」
お紺が襖を開け、奥の小さな部屋に入った。
そして布団を敷き、客人に手招きする。
「いいとこのお嬢さんを寝かすにゃ、お粗末かもしれませんがねぇ」
お紺が恐縮して言うのを、連れは、いやいや、と遮った。
だが娘を連れて行くのは躊躇っているようだ。
ただそれは、『お嬢さん』に触れるのを躊躇っているだけのようで、だから奥の部屋まで運ぶことが出来ない、という理由のようだが。
「何を躊躇ってんでぃ。すでにお前さん、娘さんに触れてるじゃねぇか」
そんな初心(うぶ)な歳でもあるまいに、と、貫七が呆れ気味に言う。
すると連れは、また慌てて娘を支えていた手を離した。
「おい! 危ねぇ!」
いきなり連れが手を離したため、がくりと倒れる娘に駆け寄った貫七が怒鳴る。
「あんたが連れて行けないってんなら、俺が連れてくぜ」
言うなり貫七は、ひょい、と娘を抱き上げた。
そのままさっさと、奥に運ぶ。
しばし呆けていた連れは、やっと我に返ったように、急いで後を追って来た。
「んじゃあお紺ちゃん、後は頼むぜ」
娘を寝かせ、貫七はさっさと階段を上がって行った。