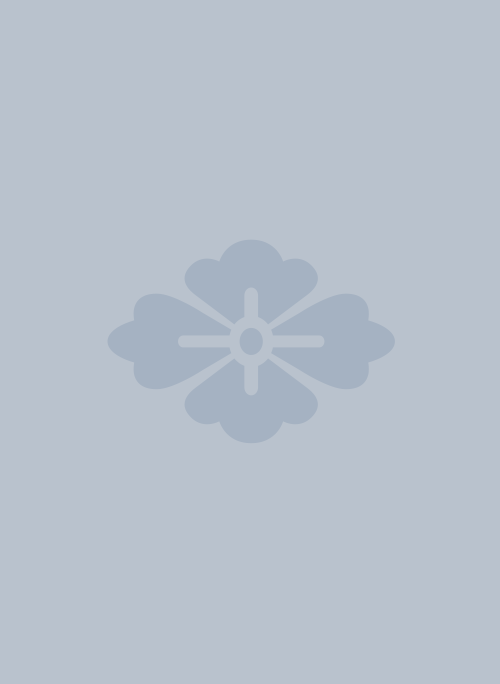「ちょっと待てよ。俺は用心棒だぜ。用心棒を夜に縛り上げておいて、何の意味があるってんだ」
ぐ、とお紺が言葉を詰まらす。
横でお由が、『ろくに働きもしないくせに』と小さくぼやいた。
「全く、お紺ちゃんは男ってものをわかってねぇ。お紺ちゃんみたいな別嬪さんが傍にいて、おあずけ食らうことほど辛ぇことはないんだぜ?」
「も、もぅもぅっ! いいいいいいい加減にしてよぅっ」
真っ赤な顔で喚くお紺に、力任せに抱き締められ、おりんは少し焦ったように暴れた。
そんな騒がしい夕餉が終わる頃、不意に今までへらへらしていた貫七の目が鋭くなった。
戸を振り返る。
同時に、微かに外で物音がした。
「……誰だい」
片膝を立て、一歩前に出てお紺とお由を背後に回す。
おりんがお紺の膝の上から降り、貫七の横に移動した。
しばらくそのまま様子を窺ってみたが、何事も起こらない。
貫七はおりんと顔を見合わせ、おもむろに立ち上がった。
「か、貫七さん……」
思わず腰を浮かせたお紺に、口の前で人差し指を立てて見せ、貫七はそろりと土間に降りた。
ぴたりと戸の横につけ、外の空気を読む。
ぐ、とお紺が言葉を詰まらす。
横でお由が、『ろくに働きもしないくせに』と小さくぼやいた。
「全く、お紺ちゃんは男ってものをわかってねぇ。お紺ちゃんみたいな別嬪さんが傍にいて、おあずけ食らうことほど辛ぇことはないんだぜ?」
「も、もぅもぅっ! いいいいいいい加減にしてよぅっ」
真っ赤な顔で喚くお紺に、力任せに抱き締められ、おりんは少し焦ったように暴れた。
そんな騒がしい夕餉が終わる頃、不意に今までへらへらしていた貫七の目が鋭くなった。
戸を振り返る。
同時に、微かに外で物音がした。
「……誰だい」
片膝を立て、一歩前に出てお紺とお由を背後に回す。
おりんがお紺の膝の上から降り、貫七の横に移動した。
しばらくそのまま様子を窺ってみたが、何事も起こらない。
貫七はおりんと顔を見合わせ、おもむろに立ち上がった。
「か、貫七さん……」
思わず腰を浮かせたお紺に、口の前で人差し指を立てて見せ、貫七はそろりと土間に降りた。
ぴたりと戸の横につけ、外の空気を読む。