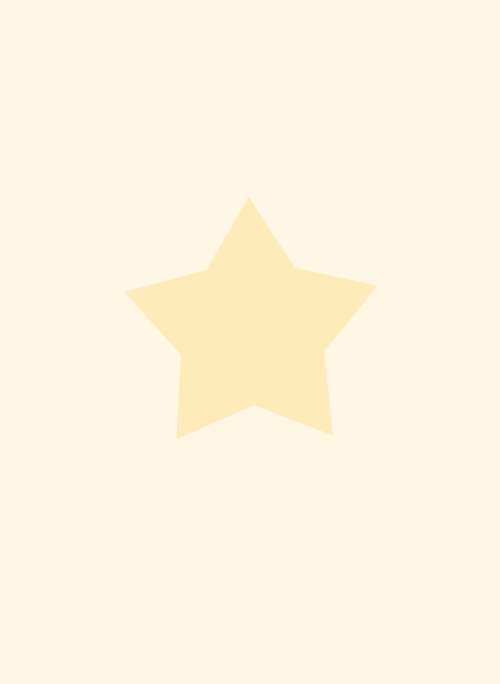ワイワイ楽しそうに準備するクラスメイトの声に紛れて、俺は誰にも気付かれないように、教室から出ようとしたが、
「ねえ、ちょっと」
と、俺を止める奴がいた。
文化祭実行委員の、近江千紗子だった。
近江千紗子は、いつもは下ろしている髪を一つにまとめていて、ダサイ眼鏡の奥にある目で、ぎろりと俺を見つめる。
「田中君、どうして帰ろうとしているの?」
「だって、することないし…………」
口をもごもごと動かせながら、俺は言った。
喋るのは、あまり得意ではない。
「ねえ、ちょっと」
と、俺を止める奴がいた。
文化祭実行委員の、近江千紗子だった。
近江千紗子は、いつもは下ろしている髪を一つにまとめていて、ダサイ眼鏡の奥にある目で、ぎろりと俺を見つめる。
「田中君、どうして帰ろうとしているの?」
「だって、することないし…………」
口をもごもごと動かせながら、俺は言った。
喋るのは、あまり得意ではない。