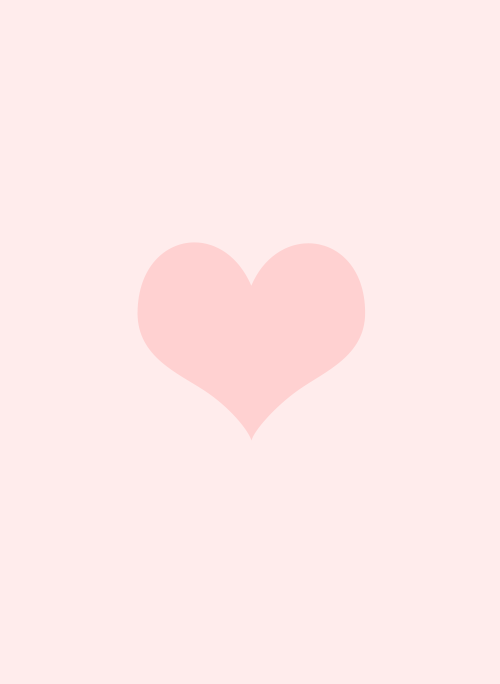永輝が優しい人なのだということは勘づいてはいたが、普段の軽い言動のせいで、彼は損をしているんじゃないかとすら思ってしまう。
菜々は和室のこたつに座って永輝とともに夕食を食べた後、アルバムを引っ張り出して両親の思い出話をした。何度か引っ越しをして、中学生のときにここに落ち着いたこと、死ぬ前まで、父は大阪の小さな料亭で働いていたこと、父と母がときどき笑顔で見つめ合っていたこと……。
「私が気づくと、照れたように笑うんです。お互い、まだ恋をしてるんだなってわかってステキでした……」
菜々はほうっと息を吐いた。
「ステキなご両親だったんだね」
「はい!」
永輝の言葉が嬉しくて、菜々は彼を見つめた。その深い色の瞳に浮かんでいるのは、菜々の過去を知った同情でも、バイト先のオーナーとしての義務感でもない。心から共感してくれているような温かさだ。
(まだ一緒にいてほしいな……)
菜々は手の中の紅茶のペットボトルをギュッと握りしめた。
「あの……」
「どうした?」
「あのっ、こ、今夜はここに泊まっていきませんか? も、もう遅くなってしまったし、こんな時間に運転して帰るのは危ないですし……」
菜々は和室のこたつに座って永輝とともに夕食を食べた後、アルバムを引っ張り出して両親の思い出話をした。何度か引っ越しをして、中学生のときにここに落ち着いたこと、死ぬ前まで、父は大阪の小さな料亭で働いていたこと、父と母がときどき笑顔で見つめ合っていたこと……。
「私が気づくと、照れたように笑うんです。お互い、まだ恋をしてるんだなってわかってステキでした……」
菜々はほうっと息を吐いた。
「ステキなご両親だったんだね」
「はい!」
永輝の言葉が嬉しくて、菜々は彼を見つめた。その深い色の瞳に浮かんでいるのは、菜々の過去を知った同情でも、バイト先のオーナーとしての義務感でもない。心から共感してくれているような温かさだ。
(まだ一緒にいてほしいな……)
菜々は手の中の紅茶のペットボトルをギュッと握りしめた。
「あの……」
「どうした?」
「あのっ、こ、今夜はここに泊まっていきませんか? も、もう遅くなってしまったし、こんな時間に運転して帰るのは危ないですし……」